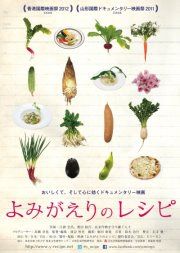秋色の展示
flowers primitiveの西別府さんのリース展を見にvigoとアートサロンARKへ。
西別府さんの作品は花の美しさだけでなく面白さ、強さ、脆さ・・・今まで気づかなかったようなさまざまな花の性質を発見することができて、見るほどに惹きつけられる。ハッとするような派手さや華やかさではなく、他の何をも邪魔しないのだけれども、静かに深く存在感を放っていて、花の生命力を感じられる。置いてあるだけで確実にその場の空気が変わって、じわじわと西別府さんワールドに染まっていく。先日教わった「花と遊ぶ」ことを思い出した。西別府さんご自身が花と遊ぶことが大好きで、それを存分に楽しんでいることを感じられる、とても素敵な展示でした。
アートサロンARKのオーナーは羊毛フェルトの造形作家のYOSHiNOBUさん。リアルなのにほのぼのとした、独特の世界感を持つ動物たちを制作している。初めての動物を制作するときには動物園に行って観察し、専門家に話を聴き、針金で骨格を作り、筋肉などの位置も正確にとる。こういった造形の基本は、元々やっていた粘土の時と変わらないけれど、フェルトと出会ってからは毛並みの方向までリアルに再現でき、固まることもない自由度の高さを得たという。フェルト素材の持つ温かさや柔軟性、軽さのせいか、動物の持つ表情自体がユーモラスで可愛いためか、ことさらにキャラクター化しなくても自然と可愛らしくほのぼのとした表情を持つ作品になるのだそうだ。たしかに、動物ってなんかずるいぐらい面白可愛い表情をするときがありますね。その特徴を作品に映し出す表現力がすごいのだ。
こちらでは定期的に羊毛フェルトのワークショップも開催している。「ここまで教えちゃっていいの?」というぐらい惜しみのない懇切丁寧な指導なのだと来場者の方が教えてくれた。カップルで来た男性の方が夢中になってしまったりもする、なかなか硬派なワークショップのよう。11月は「ヒツジ」と「オカメインコ」。可愛い・・・。もう受付は始まっていますので、モノづくり欲の高まっている貴方!ぜひチャレンジしてみてくださいね。
夕方、「古道具屋の西洋見聞録」の塩見さんを訪ねて青山へ。毎週土曜日、全国から素敵なお店が集まってくるアンティークマーケット。ふと出展ショップカードの中にさきほどのflowers premitiveさんのお名刺を発見。繋がっている~今展示に行ってきたばかりですよ~! などとあれこれよもやま話をしているうちに日も暮れて、だいぶ気温も低くなってきたのに客足は途絶えない。
みなさんも、秋風に誘われて、自分だけの宝物を見つけに出かけてみてはいかがでしょう。