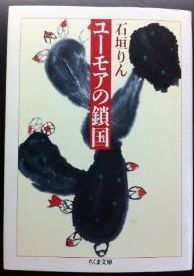九州に行ってきました 福岡・八女編
縁あってこの週末は九州へ行くことになり、今回は福岡・八女からのスタート。ほとんどお茶の産地としてしか知らなかったこの地に、少し前から「うなぎの寝床」さんという気になる存在が現れた。連絡してみると、突然だったにもかかわらず「僕が迎えにいきましょう、八女を案内しますよ」とのこと。そんなありがたいお言葉に甘えて、八女の町巡りが実現しました。
空港から高速バスに乗ること約50分・・・のはずが、渋滞でもないのに予定時間を過ぎている???「ここ八女ですか」「あ、違うよ、ここは瀬高よ!」と同乗の地元の方が教えてくれたから助かったものの、あわや熊本か!というアクシデントで迷惑をかけつつ、店に到着。ガラガラと戸を開けると、広い土間と大きな火鉢がまず目に飛び込み、花火や独楽、お茶や器や久留米絣など筑後の手仕事が、それは美しく並んでいて、まず視覚から惹き付けられる。それもそのはず、企画・デザインの白水高広さんと店主の春口丞悟さんは、大学では建築を学び、その後「ちくご元気計画」という、地域資源をより魅力的に磨くプロジェクトに関わっていた。商品をよりよく見せる、魅せる、プロなのである。「ところでその商品はどこで買えるのか」と地元の人に聞かれ、たしかに買える場所が限られている、それなら自分たちで店を開こうと二人が思い立った矢先に、八女福島の町家に空きが出たのがお店の始まり。物事がトントン進むときにつきものの、この行動力とタイミング。八女愛に溢れ、作り手の心も、買い手の気持ちもよくわかっている二人だからこそ、こんな素敵な空間が生まれたのだと納得です。
八女福島の伝建地区はもともと自分たちで地域を守る意識がとても高く、ここ数年は市民がお金を出し合って町屋を改装し、外から作家さんを迎え入れるなど、守る+αで新しい風を呼び入れて街を活性化させることにも積極的だそう。それはだんだん実を結びつつあるようだ。2時間ほどの滞在時間の中で、絵本屋さんで読み聞かせをしてもらったり、町家づくりの素敵なカフェや、まちづくりを引っ張っている酒屋の高橋さんを紹介してもらったり・・・どの店もゆっくり過ごしてみたい場所ばかり。皆和やか、にこやか、楽しそうで、い~い雰囲気です。駆け足だったのがとても残念。初めて来ても気軽にいろいろ尋ねてみたら、きっと皆さん喜んで案内してくれそうです。ほんとうに、素敵なところでした。
夕方、もうすぐ終了するPATINAさんの展示に駆け込みセーフ。Jane Muirの作品は、素朴かつ上品で、暖かみがあるのに洗練されていて、お店の雰囲気にもぴったり。vigoは、キノコをまとめて欲しそうでした。展示が終わったあとも、PATINAさんでお取扱いがあるとのこと。その後、望雲さんやキナリさんを訪ねたり、福岡県版コラムを書いてくれているお二人とご飯を食べたり。あっという間に時間が過ぎていきました。
八女のみなさま、福岡のみなさま、ありがとうございました!
大分・日田編へつづく