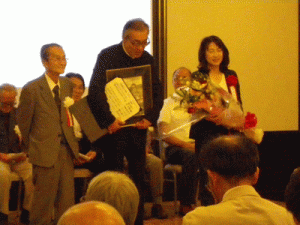元・立誠小学校特設シアターで「ある精肉店のはなし」を観た。江戸時代から7代に渡って牛の飼育から、屠畜、解体して精肉するまでをすべて一家で、手作業で行ってきた大阪にある北出精肉店の人々の日常を追った、ドキュメンタリー。

映画は、体重5~600キロもあろうかという大きな牛を、牛舎から屠場に連れてきて、ハンマーで急所を打って倒し、そこから一気呵成に血を抜き、ぶらさげて解体し、内臓の汚物や血液を洗い流し、包丁一本で売り場に出せる大きさに切り分けるシーンからはじまる。鮮度が命の現場なので、この一連の作業は驚くべき速さで手際良く行われていく。剥がれた皮はなめしてだんじりでつかわれる太鼓になる。すべての工程は家族の手でなされ、その姿は観ているこちらが汗をかいてしまうほどにエネルギッシュで、相当高度な職人技を必要とするものであるとわかる。
こんなハードな仕事の合間に、入れ替わり立ち代わり皆が食卓に集い、年に一度のお祭りで地域の人たちと仮装をして踊り、おばあちゃんの頭を息子たちが洗って散髪し、近所の人や親戚が大勢来て焼き肉パーティや年末の宴会を行う賑やかでパワフルな一家とその周辺の風景が描かれる。全編を通じて少しずつ出てくる長男の新司さんと奥さんの静子さん、二男の昭さん、長女の澄子さん、おばあちゃん、新司さんの息子さん夫婦へのインタビューが映画の軸になり、脈々と続いてきた家業への誇り、家族や地域を大切にする思い、被差別部落についての問題、と家族にまつわるさまざまな出来事をまっすぐな言葉で語る。それぞれの明るく楽しいキャラクターのせいもあるけれど、「いま」をしっかりと生きている人たちだからこそ伝わってくるものがある。
新司さんは思春期に「ケモノの皮剥ぐ報酬として、生々しき人間の皮を剥ぎ取られ、ケモノの心臓を裂く代價として、暖い人間の心臓を引裂かれ、そこへ下らない嘲笑の唾まで吐きかけられた呪はれの夜の惡夢のうちにも、なほ誇り得る人間の血は、涸れずにあった」という水平社宣言の言葉に出会い、これは自分の家のことだと思いいたって解放運動に参加する。差別に反対する言葉によって差別を知ることになるジレンマも感じたけれど、正しく知ることなしには根本から差別を無くせないというのもまた事実だと思う。新司さんの言葉はいつも問題に真正面から取り組んできた人の哲学があり明確で、説得力に満ちていた。
2012年にこの屠場が閉鎖される直前に監督が一家と出会ったのも、何かの運命かもしれない。本当に貴重な、いま観ておくべきドキュメンタリーだと感じた。同じ食べるなら、こんな風に信頼のおける肉屋さんの出所のはっきりしたお肉が食べたいと思った。命をいただくありがたさが身に沁み、誇りをもって仕事する人々の輝きが心に残った。
今後の上映スケジュール、上映会はこちら→映画館 その他の会場
上映会向け貸出もされているようです→上映会を開催しませんか?
会場となった元立誠小学校は、明治2年に開校された日本最古の小学校の一つなのだそう。建物1階の廊下には、明治~廃校になるまでの卒業写真が展示され、時代の変遷を観ることができて面白い。この地は明治30年に日本で初めて映画が上映されたという由緒ある場所で、ここで観ると映画の余韻が一層深まる思いがします。