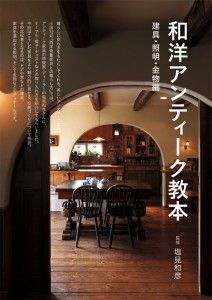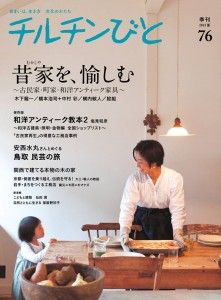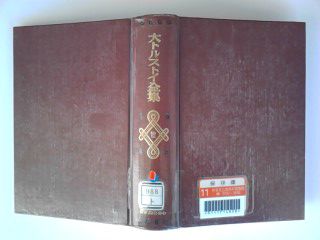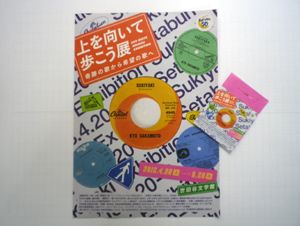神保町昨今
神田・神保町で二つの店が閉店した。一軒は、交差点近くのカメラの「太陽堂」である。私は小さいときから、写真と本が好きだったから、この界隈に、よく遊びにきた。そして、高価なライカやローライをショーウィンドウ越しに眺めたのだった。だから、「皆様のご厚情をいただいて、今日まで営業を続けてまいりましたが」という貼り紙は哀しい。大正9年の創業である、という。90年の歴史はフィルムの歴史なのだろう。
東京堂の斜め前の、本と雑貨の「シェ・モア」も姿を消した。ここには、それ以前の店構えのころから雑誌を買いに、よく立ち寄った。「この度、勝手ながら6月30日(日)をもちまして閉店致しました」という貼り紙は淋しい。
神保町は、テレビの街歩き番組などで、よく見かける。先日の『アド街ック天国』でも、古本、中華、ギョウザ、カレーなどの話題満載だったけれど、そのなかで、こんなふうに店仕舞いしていくところがあることも、記憶に残しておきたい。