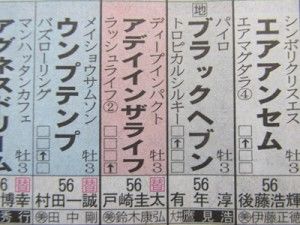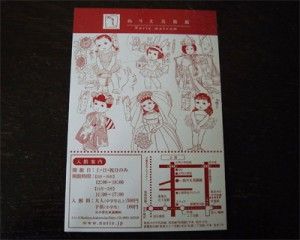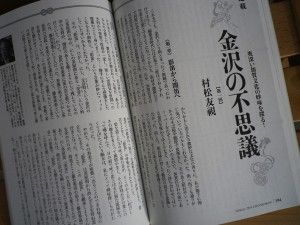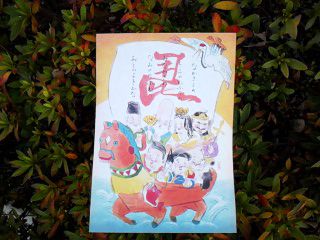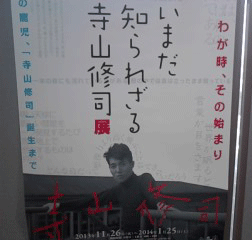嬉しか
二月、テレビ東京の『アド街ック天国』で、西荻窪が、特集された。そのなかで、坂本屋という店のカツ丼が、登場。お客さんの注文があってから、カツを揚げ、タレに浸し…… と、おいしそうに、手順が放映された。それから約1カ月。店の前を通ると、ナント、行列30 人。寒風に肩をすくめて立っている。私は、それを横目に通り抜け、坂道を下って「ウレシカ」へ。絵本 + 雑貨 + ギャラリーの店である。
世田谷の経堂から引っ越してきて、今日が、開店だ。この “ 広場 ”でもおなじみである。12時少し前につくと、ナント、店のあくのを待っているひとが何人かいる。新しい場所にきて、商売を始めるとき、これは「嬉しか」ではないだろうか。私は、「行列ができるのは、カツ丼とウレシカくらいですね」と、店のコバヤシさんに、つい余計なことを言った。そして、小さな姪のために、 『どうぶつだいすき』(イジー・ジャーチェク)と『チキンスープ・ライスいり』(モーリス・センダック)の二冊の絵本を買って帰った。