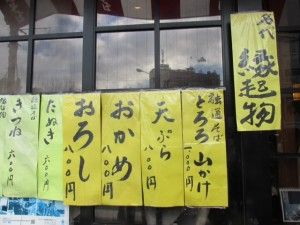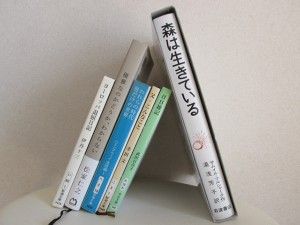新連載「変奇館、その後」開幕
「あなたの座っているところは、アスファルトですよ」と、山口瞳さんは、いった。私は、山口邸にいた。大きなガラス窓から、陽が降りそそいでいた。床はそのへんの道路と同じで、その上に座っているのだという。だからといって、冷たいとか固いとかは思わなかった。とても平らな感じがした。率直に、いいなと思った。なんといっても、堅牢で、安心だ。地震でも安心ですね、というと、地震のとき、この家はまったく揺れないで「ピッ」という音がするだけだ、ということだった。山口さんは、この家を「奇邸」と呼び、「変奇館」と名づけ、たくさんのエッセイを書いた。たとえば、こんなふうに……。
〈家のことについて書く義務があるように思われる。新建材を多用した、かなり実験的な家だからである。私が実験したのではなく、建築家が実験したのである。私自身はモルモットである。〉(山口瞳『男性自身』・奇邸)
変奇館ができて45年。山口さんが亡くなられて20年。いま、その家に暮らす長男・正介さんの実験報告続篇である。
「変奇館、その後」は、こちらからご覧になれます。