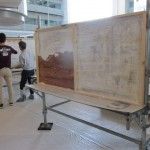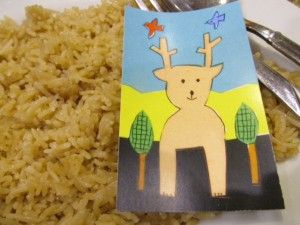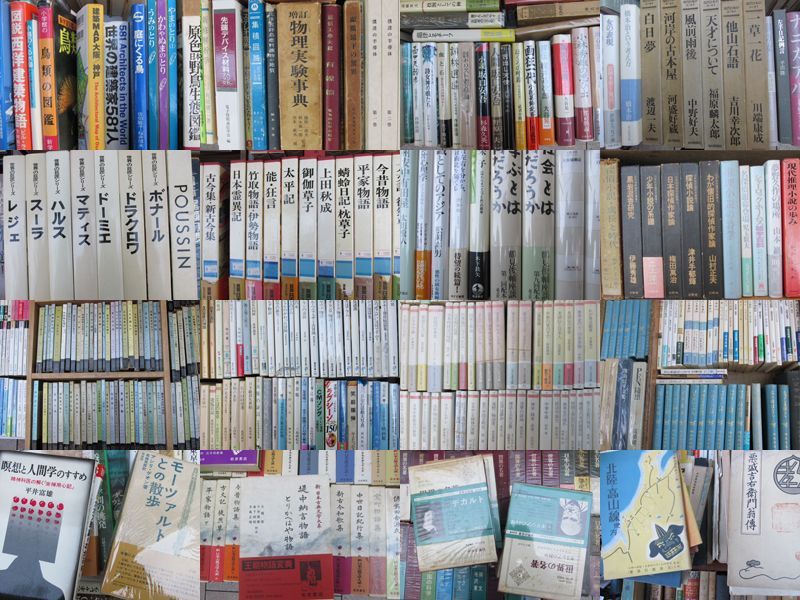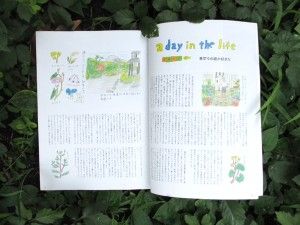「大江戸左官祭り」―土と戯る
「大江戸左官祭り」へ行くには、「大江戸線」に限る。勝どき駅で降りて、会場へ。今回の催しは、一般向けにしたようだ、という声が聞こえる。
壁塗り体験。光る泥だんごづくり。かまど塗り体験。ミニかまどづくり。泥絵の具で絵や書を書く。…… オトナもコドモも、ひたすら、撫でたり、捏ねたり、塗ったり、磨いたりしている。土と戯る。
工務店の会でおなじみの、勇建工業の加村さんとワイズの山本さんに、お目にかかる。会期中も、その前の準備期間も、昼も夜も大忙しだった、と笑う。夜も ⁈⁈ かまどが人気で、ゴキゲンだ。電気が要らない、おいしく炊ける、ということで、かわいい働き者に見える。こんなに人気なら、ぜひ、この “ ひろば ”のブレゼントにして、近々、みなさんにお届けしたい、という話になる。どうか、お楽しみに、お待ちください。