少しずつ春

節分、立春を過ぎ、
2月だというのに春らしい日があったと思えば、
昨夜は雪が舞って急に寒さが戻ったり。
そして今日、事務所近辺は
昨日の寒さが嘘のように晴れている。

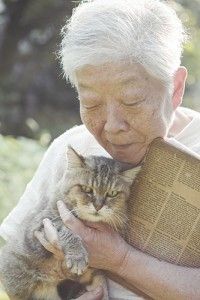
ついつい時間があると仕事をしてしまう日々。今年からは思い切って週に1日は自分の時間に使うことに決めた。
そんなわけで、昼はせりそばを食べ、久しぶりに映画を観にいった。
「FINDING VIVIAN MAIER」
オークションハウスで購入したネガの価値を見出したジョン・マルーフがヴィヴィアン・マイヤーの謎を探るドキュメンタリー。
この「広場」のコラム欄で、「私のセツ物語」が始まった。セツ・モードセミナーという、ユニークでフシギな学び舎を描くことで、教育とは何、学ぶとは何、ということが浮かび上がってくるだろう。コラムの反響は、読んでいるうちに涙が出ましたなどと、懐かしさにあふれているものが、多い。自分は、その学校に行っていたわけではないけれど、風景の描き方など教わるところが、いいですね、という感想もある。
なにを隠そう、「広場」のスタッフのMも、通っていたひとりである。当時の仕事先から、夜、セツに向かうときの楽しさについて、話していたことがある。授業が終わると、みんなお金がないから、四谷から新宿まで歩いて帰ったと、話していたことがある。それは、ステキな貧乏だった。貧乏はステキだった。みんな、夢みる生徒だった。いまも、イラストの仕事を続けるひと、ふるさとに帰ったひと…… みんなに、若者たちの昔を、描いていただくつもりである。
※「私のセツ物語」は、コチラからご覧いただけます。
寒空の中、古い地図を探しに、4.5年ぶりに国立国会図書館へ。
広い館内を、ゆっくりと過ごすことができる
お薦めの図書館だ。
※国立国会図書館は満18歳以上の方ならどなたでも登録することができる。
入館のシステムが変わり、少し戸惑ったが、
図書館独特の、空気と静けさは変わらない。
資料を複写する際は、資料を複写カウンターに持ち込み、
担当の方に複写をお願いするシステムなのだが、
重い資料を運び込むのが、結構大変なのだった。
播州織の産地、兵庫県西脇市にある玉木新雌さんのアトリエを訪ねた。ここは東経135度線と北緯35度線が交差する日本列島のど真ん中。京都からだと新幹線で新大阪まで行き、高速バスに乗り換える。隣県ながらちょっとした旅行気分。西脇市に入ると古い建物や、播州織の文字もちらほらと見え、織物の街として栄えてきた風情を残した昔ながらの街並みが現れる。そこを少し過ぎ、上野南のバス停で降りて5分ほど歩くと玉木さんの工房がある。
白く広々とした建物をキャンパスに溢れる色。絶妙な色彩感覚で織りなされるショールやウエアがずらりと並ぶのが外からも見え、建物に入る前からワクワクする。「こんにちは」とおずおず扉を開けるとスタッフさんたちが笑顔で迎えてくれた。スタッフの阿江さんも気さくに話しを進めてくださるので初対面の緊張も完全にほどけてリラックスしながら待っていると、玉木さんが現れた。まっすぐ自然体で、周りを元気にする力がこんこんと湧き出て、全く威圧感がないのに強いエネルギーのある人だった。それがアトリエ中に伝播しているせいか、働く皆さんものびやか、にこやか。生き生きと仕事されているのが伝わってくる。
洋服屋の家に生まれ服飾を学び、東京で服のデザイナーをしていた玉木さんは、はじめは一対一の対面でオーダーメイドの服作りにこだわっていたが、次第にそのやり方には限界を感じ、もっとたくさんの人に「これしかない!」と思うものを見つけて自分なりの着こなしを楽しんでもらいたいと思い始めた。それを可能にしてくれる生地を探し求めていたとき、ある見本市で出会ったのが播州織だった。糸を先に染めてから織る先染めの手法と、縦糸横糸の織りなす細やかな表現に感動するも「繊細すぎて遠目からじゃわからない。もっと大胆な色遣いにしたほうがいいと思う」と、思いついたことをそのままブースに立っていた人に告げると、なんと職人さん張本人。播州織の師匠となる西角さんとの出会いだった。彼は、「ほなそうしてみよか」と玉木さんのリクエスト通りのものを後日わざわざ作ってくれたそうだ。それが今日のtamaki niimeブランドを産み出すきっかけになった。当時、玉木さんが希望したような大胆な色づかいの生地にはあまり需要がなかったが、せっかく作ってもらったものを生かさねば、とそれらを買い取り、自分でこの生地を生かした作品を作ろうと思い、この地に移り住み、古い織機を買い取って、職人さんに教わりながら見よう見まねで生地づくりを始めた。さらりと言うが、この潔さ。どれだけ肝っ玉が座っているのだ!?と思った。
ほぼすべて一点もので色合いが違い、手織りのような柔らかで贅沢な触感のショールを、どうしてこれだけ求めやすい価格でしかも大量に作れるのか?聞くと、大量生産をしてきたこの土地では受注ロットも大きく、いくらこだわりを大切にしていても小ロットではコストがかかりすぎる。産業を残していくことも考えてある程度価格を抑えながらオリジナルの物づくりができる方法を考えた。そして昔ながらの機械を使いつつも着物やシャツの生地とは異なる緩い密度で、ふんわりと柔軟性を出す独特の織り方を産み出したのだそうだ。
玉木さんは毎日、その日に使う糸の色を決める。棚を見ているとその色が浮き上がってくる。普段から目に入るものはなんでも意識するけれど、わざわざ糸選びのためにインスピレーションの源を探すということはないという。流行も一切無視。体から出てくる色だ。それでも実際に織り上がるものがイメージと違うことはしょっちゅう。そのたびにちょっと待った!と機械を止め、糸を掛けかえることもしょっちゅう。その手間暇をかけたいがための自社工場だ。スタッフさんもニット専門、織り専門、と一応分かれてはいるが、初めのうちはすべての工程を知ることから始まる。現在は、玉木さん一人でなくスタッフ皆さんでデザインや糸選びなどのアイディアを出し合い、次世代を育てることも既に始めている。
玉木さんのものづくりは、伝統を踏襲しつつもかなり大胆でオリジナル。それゆえ始めは地元からの拒否反応もあったそうだが、常に理解し応援してくれる人もいた。なによりここで生まれたものを喜んで使ってくれる人たちがいた。ともあれ思いついたら試す。自らやれることは全部やる。周りに無理を通さない。これでダメならああやってみよ。玉木さんの辞書に言い訳という文字はない。今後の夢は「日本のへそ」たるこの西脇市から、世界の人にtamaki niimeのつくるものを届けること。そして、世界からこの場所へ遊びに来てもらうこと。そのため秋には念願だったもう少し広い場所に移って、新たな展開を準備中だという。この人ならば無理せず自然に「世界」に手が届くだろう。言葉の隅々にそう思わせる説得力があった。
話を聞き終え、阿江さんにアトリエを案内していただいた。ガシャンガシャンとリズミカルな織機の音が響く。玉木さんの「閃きの糸」が置いてある棚も、色指示の表もすべてオープン。少し離れたところにあるアトリエで、さらに古い織機を見せていただいた。黒光りした鉄と木の骨組みが重厚堅固で、昔のモノづくりの確かさを物語る。同じ場所では織専門のスタッフさんが熱心に新しい柄を織っている最中。古いものを大事に扱いながら新しい挑戦をたゆまず続ける「温故知新」を体現しているアトリエだった。
最後にお店をじっくり拝見させてもらった。見れば見るほど欲しいものだらけで右往左往しているうちに、不思議なことに自分のためにあるような色が見つかる。身に付けるとふんわり優しく、温かく、バイアスを生かして形が自由自在に変化する。「邪魔くさいのは嫌」という玉木さんの作るコットン作品は、洗濯機で洗ってOKの気軽さもいい。
2月のプレゼントは、tamaki niimeさんオリジナルの万能ウォーマー“boso”の中から春に向けての4色を選びました。この柔軟性の高さ、色の美しさ、ぜひ味わってください。どうぞお楽しみに。
以前は、お蕎麦屋さんだったのですが、
閉店してしまい…
なんとか建物を残したいという声が多く
プロジェクトが立ち上がって
残った店舗をカフェに改装。
リニューアルオープンとなったそうです

とにかく、居心地がいい♪
のんびり本を読んだり
ゆっくりお話をしたり…
お店に流れる時間が
何かと忙しくあわただしい日常を
忘れさせてくれます♪

家から歩いていける距離に
こんな素敵なカフェができて
幸せ♪
実際にお店で使われている
波佐見焼のカップも購入できます♪
これから、春になって暖かくなったら
お店のお庭も楽しめそう♪
夜遅くまで営業しているので
仕事のあとの
自分時間もここで楽しみたいなと思う
amedioでした\(^o^)/
木の玩具などでおなじみ、キッコロが、“ 神保町いちのいち” でお店を出している。行ってみた。お客さんに対応する合間に、うかがった話。………
ここでは、ネコのモノが動きますね。前にやらせていただいた時、お客さまとお話ししていると、ネコのモノを探している方が多いんですね。今回は、事前にカッティング・ボードや一輪挿しに、ネコをあしらってみましたが、やはり好評です。そんなふうに、土地土地で売れるモノが、ちがいます。雑司ヶ谷の手創り市では、動物の形をしたブローチが、人気。色味にも土地柄があって、長野方面ですとナチュラルな木の感じ。名古屋方面ですとグリーン、横浜ですと赤の入ったモノが売れました。こういうのがウケるだろうと、つくっていくと反応がなかったり、少ない品物がよく出たり、ヨミのはずれること、しょっちゅうです。材料の木は、ブナが主で、ブナは木目があまり主張しないし、色をつけてもキレイにでるんですね。…… そうそう、ここでは、キューブ・パズルも動きますね。立方体をつくるパズルですが、本屋さんの中のお店だからか、パズルのお好きな方が、よくいらっしゃいますね。神保町は、ネコとパズル !
この催しは、1月25日(月)まで。三省堂書店、神保町いちのいち で開かれています。ぜひ、お立ち寄りください。