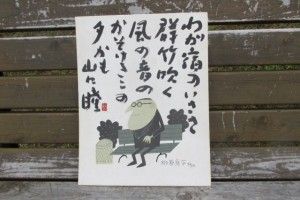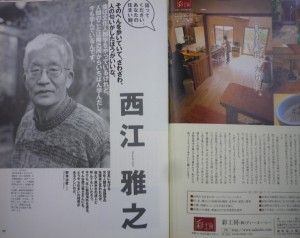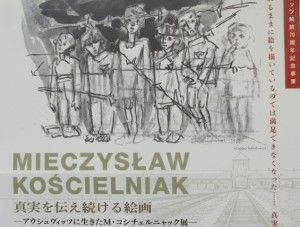アルフレッド・シスレー展へ
アルフレッド・シスレー展 — 印象派、空と水辺の風景画家 —(練馬区立美術館。11月15日まで)に行った。
最寄りの西武池袋線・中村橋駅から美術館へ向かう人の多いことに、驚く。絵葉書売り場の列に驚く。そして、たくさんの川や河や川辺や河畔や橋や水や空や雲や樹樹や草草を、たのしく見た。
帰り道。
〈どんな川であっても、私は、水のある風景、橋のある風景が好きだ。そこに労働があり、暮しがあり、知恵があるのである。一口に言って、絵になるのである。〉…… という山口瞳さんの文章(『月曜日の朝』)を思い出した。