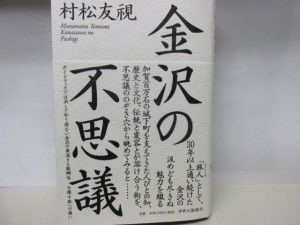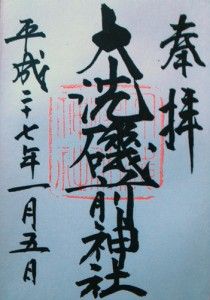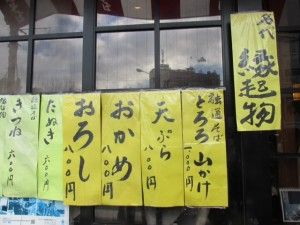初スキー
今まで、スノボに何度か行ったのですが
どうにもこうにも…上達の兆しがなく
怖いし、痛いし、つらい…
もう、絶対雪山なんて嫌だ!!と 思っておりました…
…が…
旦那さんは、そんな私を見て
「スノボだからきっと苦手なんだよ~!
今年はさぁ、スキーやってみない?
無理だったらまた考えればいいし
やってみなきゃわからないじゃん!」と
すごいポジティブさで私をぐいぐいと引っ張り
福島のスキー場へ2泊3日行ってきました
当日は天気も良く気温も高く 良い天気でした♪
スキースクールに入り数時間
写真を見ると、初心者感丸出しですが
私…笑ってますね(笑)
実は、とても楽しかったです(笑)
全然速度は出ていないのですが
シューっと走れている感覚(自己満足☆)
スノボの時は怖くて転びまくったリフトも
スキーだと一度も失敗なく大丈夫でした♪
一緒に初心者スクールを受けていた方と
リフトに乗っている間、話をしていたところ
「この年になって初めてスキーをするとは…
でも、東日本大震災で、友達をたくさん亡くし
いつ死んでしまうか本当にわからないと思って…
《人生やれることはやっておこう》
《レッスンを受けて少しでも上達して
家族一緒にスキーを楽しみたい!》と思ったの」
と話してくれました
そうですよね…
こうやって毎日過ごしていること
毎日が来ることは本当に奇跡
ちゃんと日々過ごせることに感謝しながら
私もやれることは たくさん挑戦して
悔いのない毎日を過ごそうと
改めて思ったamedioでした!