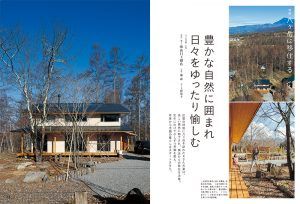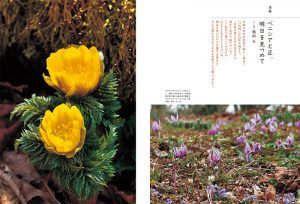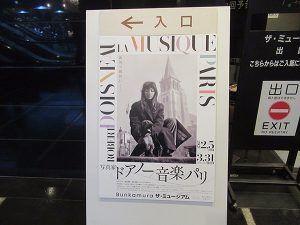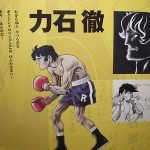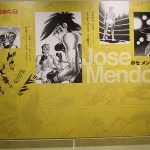コハルアンとうるしびと〈神楽坂デイズ〉
この「広場」の好評連載「コハル・ノート モノと語る」(はるやまひろたか)のなかで、「会津の塗りもの」について、こう書かれている。
〈 先人たちの知恵を使ってコーティングした、生活のための木の器。そんな観点で漆器を見直せば、高いと思われた敷居は、少しだけ低く見えるようになるかもしれません。僕自身、漆器についてはそういう見方で接してきたので、お椀も家ではがんがん使ってしまいます。味噌汁用の器というポジションにとどまらず、洋風のシチューやスープなどにも。……〉
そして、日々愛用している器をつくる、村上修一さんについて、話が展開する。
その村上さんが、『チルチンびと』107号に「うるしびと」というタイトルで登場。〈会津若松市内の山間部、山道の先に、ウルシの林はある。……
漆掻きの作業手順は至ってシンプルだ。まずはカマで木表面の硬い樹皮を削り取り、表れたやわらかい樹皮にカンナで傷をつける。傷から染み出してくる樹液をヘラで掬い取り、掻き樽にためる。単純な繰り返しだが、足元の悪い山中を動き回る重労働だ。……〉そして、器にうるしをほどこしていく様子も細かく見てとれる。
コハルアンは、地下鉄東西線の神楽坂駅下車。新潮社の一つ手前の通りを入って左側にある。店主のはるやまさんと村上さんの手による器が、出迎えてくれるだろう。
『チルチンびと』春 107号 好評発売中