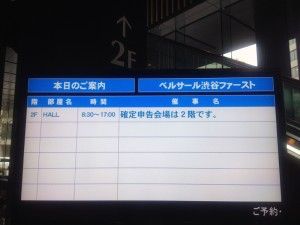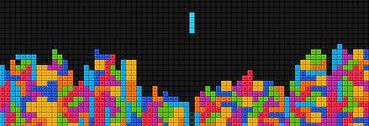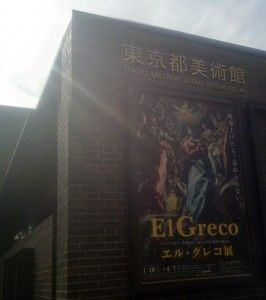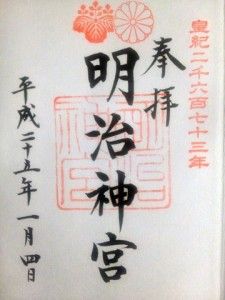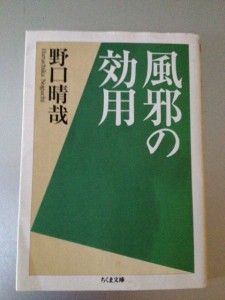日常の贅沢
九州出張帰りのvigoからは、大川お番茶会さんの「ごぼう+黒大豆のやさい番茶」、takekoからは、うきは百姓組さんの「梨のドライフルーツ」をいただいた。
この番茶は、ちくご産のカラダにやさしい素材を使用。お茶を楽しんだあとは、ごろごろと入った「ごぼう」「黒大豆」を食すと香ばしくておいしい。
大好きな「梨」は、砂糖、添加物を一切使わず、素材のままのドライフルーツに。梨独特のシャリシャリした食感がたのしくておいしい。
どちらも他の種類をいくつか揃えているようなので、お取り寄せしてみようかなと、こんな日常の贅沢がうれしい。