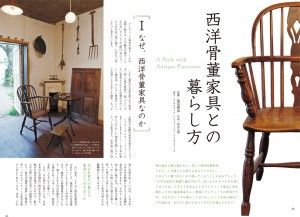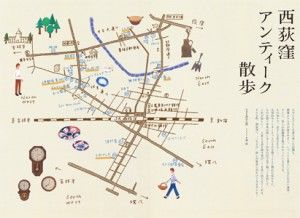薪割り
幸田文さんの薪割りの話は、いいよ、と友人が教えてくれたことがある。それは『父・こんなこと』(新潮文庫)のなかにある。「薪割りをしていても女は美でなくてはいけない。目に爽でなくてはいけない」と父親に言われ、風呂のたきつけをこしらえる話を、こんなふうに書いている。
庭木は檜は楽だったが、紅梅は骨が折れた。抵抗が激しく手が痺れたが、結局これもこなして焚口へ納めた。しまいには馴れて、ふりおろした刃物がいまだ木に触れぬ一瞬の間に、割れるか否かを察知することができた。(「なた」から)
『チルチンびと』74号〈特集・火は我が家のごちそう〉を読んでいると、あちらこちらに、薪の話が顔を出した。それで、友人の話を思い出した。
幸田さんは、父の教えたものは技ではなくて、これ渾身ということであった、と書いている。ストーブや暖炉や風呂で暖まることができるのは、薪に込められた気持ちが熱いからだろうと、私は思った。


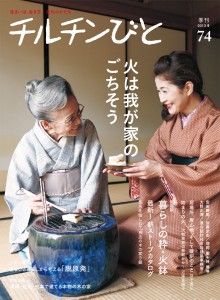

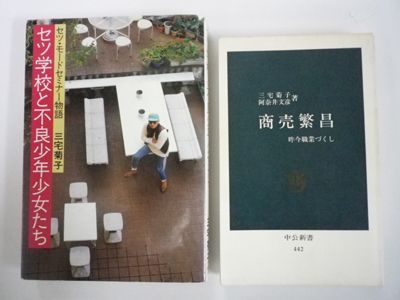
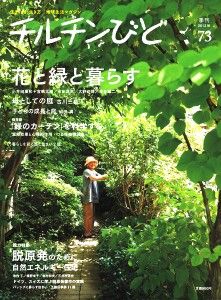

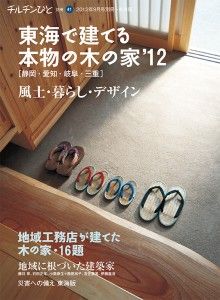
 ちいさな木の教会誕生のイキサツが、『チルチンびと・別冊41号・東海版』(7月
ちいさな木の教会誕生のイキサツが、『チルチンびと・別冊41号・東海版』(7月