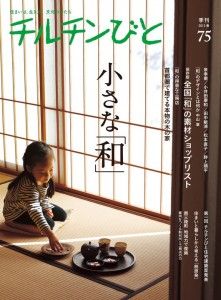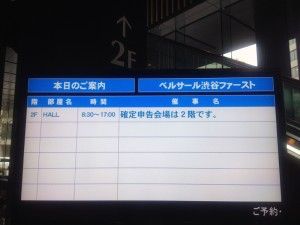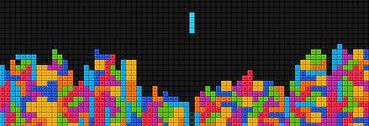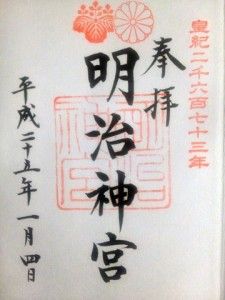小さな「粋」

『チルチンびと』75号の “ 小さな「和」” という特集を読んでいて、「和」というのは「粋」のことかもしれない、と思った。
粋といえば、Fという下駄屋の方のこんな話を、切り抜きに見つけた。「あたくしども、手を拝見すれば足の文数がわかります。足の大きさによって、鼻緒のすげ具合を加減しますが、昔の粋なお客さまは前つぼをきつく、きつくとおっしゃいます。深く履くのはヤボだとおっしゃって、爪先につっかけるようにして足早にさっさとお歩きになる……」
友人が「息子がどうにか、大学を卒業した」と言う。よかったじゃないか、と答えると 「 なに、下駄を履かせてもらったんだろ」と笑った。下駄を履かせる、というのは、採点を高めにあんばいしてもらった、ということだろう。あまり、下駄も見かけなくなった今、こんなことばも、通用しなくなる。ヒールをつけてもらう、とでもいうのだろうか。まさか。
(『チルチンびと』75号は、ただいま発売中です。)