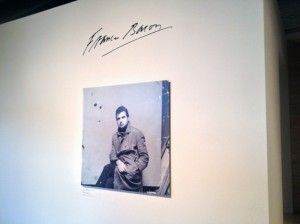気仙沼復興応援号 その3 –車窓より鹿折地区見学-
気仙沼横丁を後にして、お昼ご飯の場所へ向かう途中
(鹿折地区)にそれはありました。
気仙沼から打ち上げられた第18共徳丸です。
鹿折地区は、かなり内陸なので、ここまで津波が
来たのだと思うと本当に恐ろしい光景でした。
そして、この船を解体するか、保存するかで
話が進んでいないそうです。
このような大きなタンカーが流れてきたことにより
自宅や街全体が押しつぶされていくのを目の当たりにした被災者も
数多く、解体を望む声が多いとのこと。
この船を見るたびに、あの日のことを思い出すし、
悔しさや悲しさがこみあげる…
そのような被災された方の気持ちも
現地に行ってみると本当にひしひしと伝わります。
やはり、新聞やテレビで見るのと
現地で自分の目で見るのでは受ける印象が
全然違います。
私も、地震があったことを風化させてはいけないと
思いますが、実際に現地に行くと
まだまだ復興と呼ぶには時間がかかることがよくわかり
保存することばかりにお金を使うのではなく、
今生活している人たちが、元の生活を取り戻すために
お金を使うべきだと強く思いました。
前回、ご紹介したような仮設の商店街の中には
観光客が利用しやすい場所に
建てたために、現地の高齢者の方が
なかなか利用できず、何のための、誰のための
商店街なのか?!という現状があるということも
現地の方がおっしゃっていました。
復興に向けて、観光客を呼び
街を活性化したいという想いと
実際にそこで生活をしている人たちの想い
うまく、バランスを取ることの難しさも感じたamedioでした。