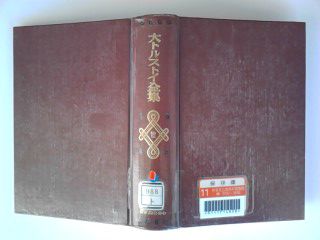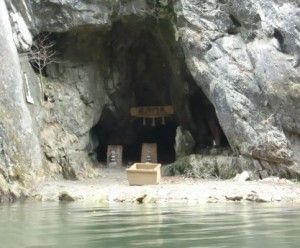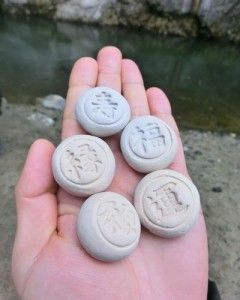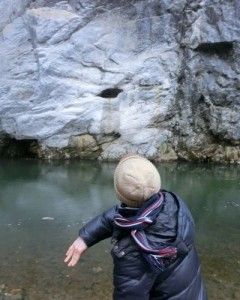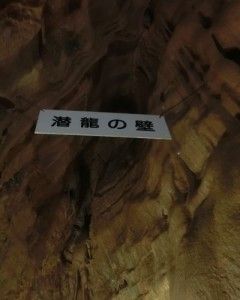気仙沼のツアーが終わり、一ノ関にて一泊。
夜ご飯は地元のものが食べたいなぁと調べてみると
一ノ関では一口餅が有名とのこと。
一関・平泉の方々はお餅をよく食べるそうで、バリエーションも豊富♪
この日の夜、お邪魔した「三彩館ふじせい」では
8種類の味のお餅と、お雑煮がセットになった「ひと口もち膳」をいただきました。

上段右から…納豆もち/あんこもち/しょうがもち
中段右から…くるみもち/お口直しの大根おろし/ごまもち
下段右から…じゅうねもち/ずんだもち/えびもち
右のお椀がお雑煮です♪
どれから食べるか迷ってしまうほど、かわいらしいサイズと色彩♪
わたしのお気に入りはじゅうねもちとお雑煮でした♪
じゅうねとは、エゴマの実でお砂糖が入っているので
ほんのり甘く、とても香ばしい味がします。
また、お雑煮は、なんといっても出汁がおいしい!
根菜もたっぷりでした!
翌日は、雨の予報でしたがぎりぎりのくもり空。
一か八かで「猊鼻渓」の川下りへ行きました。

川下りといってもここは川の流れが穏やかなので、
一往復してくるという珍しい舟下りです。
風が強く一度乗船したけれども、「降りてください」と言われ
もうだめかなぁと思いましたが、奇跡的に風がおさまり出発!!
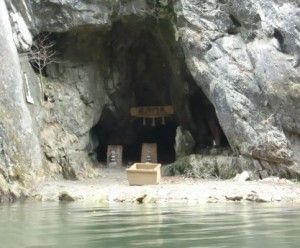
途中には「運玉投げ」といい、対岸の岩の隙間に
文字が書かれた運玉を投げ、穴に入れば願いが叶うという
運試しも♪
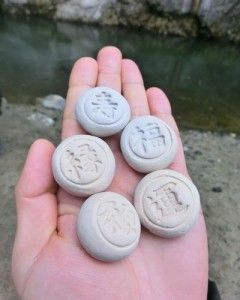
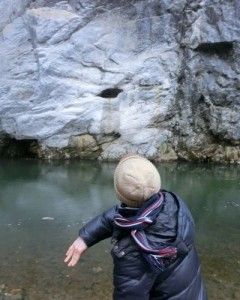
私は…コントロールが悪く2メートルほどでポチャン…
うそうそ~(涙)と嘆いていると
旦那さんが「えい!」と2つも入れていました!
ただ、一生懸命投げすぎて、どの文字が穴に入ったのか
わからず…(笑)
でも、きっと幸運が訪れることでしょう♪
船から降りた後
すぐ近くにあった食堂でお昼ご飯をいただいていると…
お店のおばあちゃんが、そーっとお菓子や
山菜をテーブルに置いて去っていくのでした♪
優しいおばあちゃん♪
鮎も美味しかったですよ♪


その後、近くの鍾乳洞へお散歩。

もともとお化け屋敷とか
暗いところが苦手なamedioは
入口の自動ドアで「怖いよぉ!」を
連呼しつつ、中を進みました。
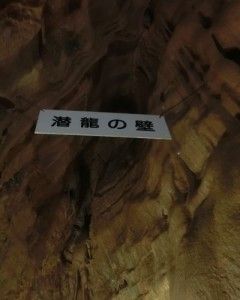
しばらくすると、かなり慣れてきて
写真を撮る余裕も♪

写真だとわかりにくいのですが
地底湖はとても水が澄んでいて
きれいでした(^_-)
1泊2日
いっぱい考えさせられて
いっぱい美味しいものもいただいて
いっぱい楽しい思い出もできました。
今度また東北に来た時に
もっともっと東北の方の笑顔が
増えていますように!と
心から願うamedioでした♪