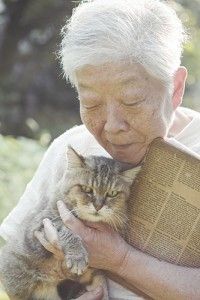ジョルジョ・モランディ―終わりなき変奏

「孤高の芸術家」とも呼ばれている、静物画が有名な画家、モランディ。
彼は、ほとんど故郷イタリアのボローニャから出なかったという。
公式インタビューを受けたのは2回のみで、
「ほっておいてくれ」と言いながら制作に没頭したそうだ。
画面の中のコントロールされた空間。
静物を正確に同じ位置に配置し、同じ光があたるよう、
テーブルにマーキングしていた。
モランディは黒しか着なかった。
ネクタイも黒か、ネクタイなしの開襟シャツだった。
というのも印象的だった。
・2015年12月8日~2016年2月14日@兵庫県立美術館
・2016年2月20日~4月10日@東京ステーションギャラリー
・2016年4月16日~6月5日@岩手県立美術館