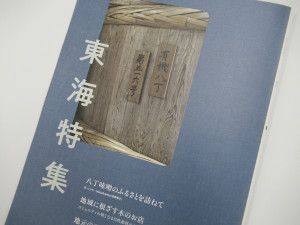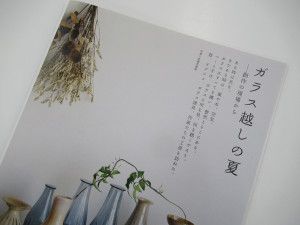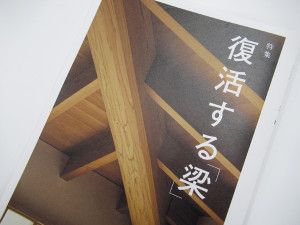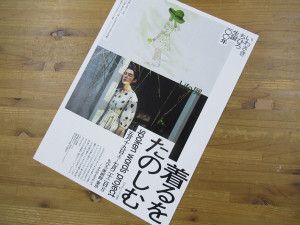1999年6月23日。セツ先生は、亡くなられた。
『セツ学校と不良少年少女たち』(三宅菊子著・じゃこめてい出版)をいまでも、懐かしく読み返すことがある。
たとえばそのなかの「ヘタクソが情熱を燃やして変わるとき」という章では、こんな言葉。
〈セツの2年間は、色をタブロオで、形をデッサンで勉強して、どうやら絵ということがおぼろげにわかってくる時間。絵描きにならせるための教育でも何でもないんです。ただ、ここで描いているうちに、その人の、その後の感じ方、生き方を変えると思う。あとは、そこから先は知らないよ。デザイナーになろうが、絵描きになろうが、勝手に自分で勉強してちょうだい。〉
……
セツに通った方々が、想い出を描く 「私のセツ物語」は、好評連載中。コチラからごらんいただけます。
2018/06/22 morimori, 書籍, 未分類
AUTHOR:chilchinbito


『ミラクル エッシャー展』に行ったのである。
上野の森美術館(7月29日まで)に行ったのである。
「だまし絵(トロンプ・ルイユ)」で知られる20世紀を代表する奇想の版画家 ……デジタル時代の今だからこそ、「版画」にこだわり続けたエッシャーの偉業を再認識できる貴重な機会となることでしょう。 …… と、パンフレットにある。
たくさんの作品を見ての帰り、カフェに寄ったのである。エッシャーにちなんだ「ミラクルパフェ」を頼んだのである。どんなものか、写真をごらんください。炭火バニラ使用と、メニューにある。このパフェは、なにを語るのか。
会場の解説に〈エッシャーは、作品に過剰な意味を読解することを嫌った。〉とある。考えないようにしよう。これが、950円で高いかどうかも、考えないようにしよう。
2018/06/18 morimori, イベント, 食べ物
AUTHOR:admin
今年最初に見た花火は
レインボーブリッジ越しに見た
「スターアイランド 2018」という
お台場で行われた花火でした♪
現地では、最先端のテクノロジーとの融合で
多くのパフォーマーが参加し
ダンスがあったりファイヤーパフォーマンスがあったり
音楽やライトの演出もあるらしいのですが
私は、対岸の埠頭の穴場スポットで
花火をゆったり楽しみました♪
対岸なので派手な演出や見られませんでしたが
花火のドーンドーンという音が
身体に染みこんできて
とても心地よかったです♪





各地で行われる夏の花火大会が今から楽しみな
花火大好きamedio( *´艸`)でした
2018/06/16 amedio, イベント
AUTHOR:chilchinbito

『チルチンびと』96 夏号の「ガラス建具をオーダーする 」というページを開いてみた。「窓辺に夢を」というサブタイトル。季節によって、気分によって建具の衣替えは、いかが、という提案だ。窓、間仕切り、扉を自由自在。楽しく美しく、変化させる。その作品を東京・西荻窪の建具店「駱駝 (らくだ)」の山本利幸さんがつくっている。
山本さんは、この「広場」のコラム「今日もアンティーク日和」でも、おなじみだ。ステンドグラスを手がけ、アンティークの世界に入り、ガラス建具へとすすんできた。それにしても、なぜ「駱駝」? コラムで、こんなふうに話している。
〈駱駝って、店の名前をつけたのは、ホント、他愛もないことで…… 候補はいろいろあったんですよ。ガラス中心に商売をやるから、漢字でいきたいとは思っていました…… 大きな烏と書いて、オオガラスと呼ぶとかね。でも、単純に毎日、ラクだ、ラクだと言えるようになりたいと思ってね。それが、ホントですよ。現実は、全然そうじゃないけどね……〉
………
『チルチンびと』96 夏号は、好評発売中。
『チルチンびと広場』のコラム「今日もアンティーク日和」は、コチラから、どうぞ。
2018/06/12 morimori, その他
AUTHOR:chilchinbito
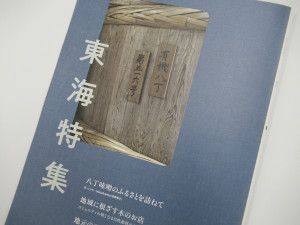
『チルチンびと』96 夏号は、6月11日発売です。今号の特集は、
復活する「梁」
ガラス越しの夏 ー 創作の現場から
東海特集・八丁味噌と木の家
の充実三本立て。
〈東海特集〉には「八丁味噌のふるさとを訪ねて」という minokamoさんの「カクキュー」からの、芳醇レポートがあります。
……
まずは、よい香りが漂う味噌蔵を案内していただきました。大きな木桶が並ぶ姿は、美味しいものができるに違いない ! と感じる光景。木桶は高さ1.8メートルもあり、上には山型に美しく積まれた石。この石を積むには10年以上の修業が必要で、重心が中心に向かうよう石の向きが少し斜めになっています。この積み方によって揺れると締まるようになっており、これまでに起きた地震で一度も崩れたことはないそう。
……
このほか、地域に根ざす木のお店、地元の工務店がつくる、心地よい木の家5題 などの話題も満載です。
……
『チルチンびと』96 夏号は、6月11日発売です。お楽しみに。
2018/06/08 morimori, 書籍, 未分類
AUTHOR:chilchinbito
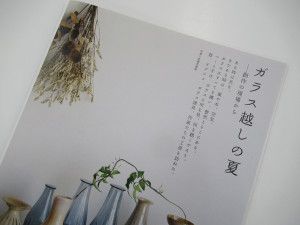
『チルチンびと』96 夏号は、6月11日発売です。
今回の特集は、
復活する「梁(はり)」
ガラス越しの夏 ー 創作の現場から
東海特集・八丁味噌と木の家
の充実三本立て。
特集〈ガラス越しの夏 ー 創作の現場から〉は、ガラス作家、ガラス建具店を訪ねて、レポートします。たとえば、草花ガラスをつくる 藤木志保さん。その記事から。
……
藤木さんのガラスは、植物から取った型からつくられている。川沿いに生えた草を一つひとつ眺め、手折る。採取するのは、形や表情が素敵だと思うもの。ガラスに置き換えるとどうなるだろうと考えて……。「植物は一度型を取ってしまうと萎れてしまう。命をいただいているという感覚です」。……
このほか、keino glassさん、荒川尚也さん、西荻窪の建具店・駱駝、も登場します。
……
『チルチンびと』96 夏号は、6月11日発売です。お楽しみに。
2018/06/07 morimori, 書籍, 未分類
AUTHOR:chilchinbito
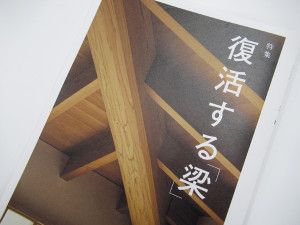
『チルチンびと』96 夏号は、6月11日発売です。
今回の特集は
復活する「梁(はり)」
ガラス越しの夏 ー 創作の現場から
東海特集 ー 八丁味噌と木の家
という充実 三本立て。
特集〈復活する「梁(はり)」〉は、見事な梁のある家を、実例たっぷりにご紹介します。そして、建築家・泉幸甫氏は、「梁の美学」をこう書きます。
…… しかし、見られるからと言って、技巧的に妙にきれいにすることにこだわりすぎると、それもいやなものになる。誠実に、きちっとした仕事になっていればそれでよい。それは人柄を見るようで、梁を見せるというのは人柄をもろに見せているようなものかもしれない。案外奥深い世界なのだ。……
梁は人なり、か。
………
『チルチンびと』96 夏号は、6月11日発売です。お楽しみに。
2018/06/06 morimori, 書籍, 未分類
AUTHOR:chilchinbito
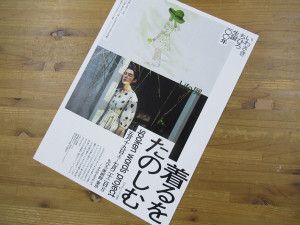


いわさきちひろ生誕100年、ということで、今年は、それにちなんだ展覧会が、あちこちでひらかれるようだ。
『着るをたのしむ』(ちひろ美術館 ・東京。7月22日まで)も、その一つ。
サブタイトルは「よみがえるセンス」。ちひろのセンス、その絵や人物についてのイメージから、あらたな作品としての生地や服をつくる試み。
「大人になること」と題した文章も、展示されている。
人はよく若かったときのことを、とくに女の人は娘ざかりの楽しかったころのことを何にもましていい時であったように語ります。けれど私は自分をふりかえってみて、娘時代がよかったとはどうしても思えないのです。……
そして、このあとに、かといって私が不幸な娘時代を送ったわけではないが……とつづけ、こころの微妙を語るのである。
2018/05/31 morimori, イベント
AUTHOR:chilchinbito