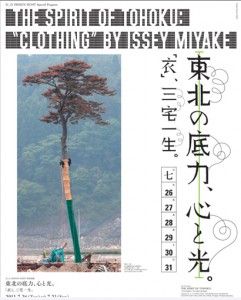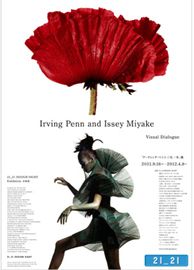北陸巡回報告
今回は、北陸[富山、石川、福井]を回ってきました。
台風の影響も心配されましたが、なんとか予定以上の54軒を尋ねる事ができました。
そして、無事に昨日車で帰って来れました。
富山県の「junblend」さん、「FUTAGAMI」さん、「能作」さん、石川県の「flatt’s bakery & cafe」さん、「gloini」さん、福井県の「GENOME」さんにはいろいろと情報を頂き、石川県の「アルムの森」さんは同じ能登出身と言う事もあり、「3人で車で東京から来たのか。これを食料にがんばれよ。」とパンをいっぱい詰めた袋を手渡してくださりまして、本当に皆様どうもありがとうございました。
また、地域主義工務店の会の富山県「インベンションハウス」さん、福井県「住まい工房」さんにも一緒に回って頂きまして、ご協力どうもありがとうございました。