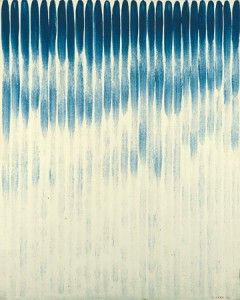鬼師という職業
今回の出張、坂田工務店さんのある東広島からの出発となった。
こちら東広島市西条の街並みは非常に特徴があって、どこの家も
赤茶色の瓦屋根になにか突起物がくっついている。
なんとなくその様子を眺めていると、タイルびとが
「ここの瓦はなんでみんなあんなに赤い色してるんですか」と聞く。
瓦は英語に訳すとタイルというだけあって、さすがの食いつきっぷりだ。
坂田工務店の高原社長によると、赤い色はこのあたりの土の色。
また、言われて初めて気づいたのだけれど、瓦屋根に乗っかった
飾り瓦の種類が豊富なのだ。鯱、鳩、鷹、波、宝船…などなど。
あまり大きくなくて鳩など止まっている様子はとても可愛い。
鬼瓦もあり、大黒瓦もいる。「平和」とか「福」「魔除け」など
それぞれに意味があるみたい。さらに屋根棟も結構高い家があり、
わたしがやっとまたげるかぐらいの高さがあるらしいが、この棟の
側面に龍が居たり、瓦を組み合わせて透かし模様になっていたりと、
とにかく非常に凝った屋根ばかりなのだ。装飾の数や棟の高さなど
多少の差はあるけれど、どこの家もだいたい揃っているので、
緑の田園風景に赤瓦が映えて美しく、圧巻だった。こういう景観は
実際に目の当りにすると、守らなくてはもったいないと思わせる。
タイルびとの瓦への食いつきがあまりにもすごいので、突如、
高原社長の計らいで「鬼師」のところに連れて行ってもらえることに。
「鬼師」とは鬼瓦含め、飾り瓦をつくるひと。かっこいい響き。。
みんなで鬼師にあこがれながら会いに行く。
実際お会いしてみると、鬼瓦窯元「賀茂窯業」の鬼師、元岡さんは、
「鬼」とはほど遠いイメージの温厚な穏やかな方。
この日はとても暑かった上に、さらに工房内は非常に暑かったけれど、
忙しい中嫌な顔ひとつせず丁寧にいろんな話をしてくださった。
鬼瓦、思った以上に大きかった。はじめて鬼瓦をつくると、大抵
泣き顔になるらしい。見せていただいた瓦は、ぐっとこちらを
睨みつけて、ものすごい迫力だった。。もう凹凸が尋常じゃない
彫りの深い顔立ちなのだ。この顔を創るのは、相当気合が要りそう。
焼いたとき、割れてしまうことがあるので必ず予備をつくる。
そして大きい物だと乾かすのに3か月かかる。急に乾かすと
割れてしまうので、温度を変える=場所を変えながら
ゆっくりゆっくりと乾かすのだ。これが1か月もの、これが2か月もの、
と、だんだん土の色が変わっていく様も見せてもらった。
なんという手間のかかった作業なのだーーー。
「鬼師」。男たるもの一度目指してみたい職業という気がする。
- 迫力!!
- 鬼だけじゃない。大黒さんもいます
- 瓦と飾りは壊れないようくっついている
- 焼かれるのを待つ鯱
- 鬼師とタイルびと
- 赤瓦の民家が立ち並ぶ