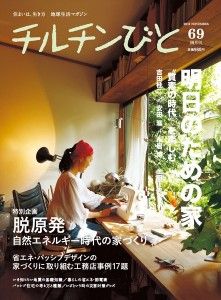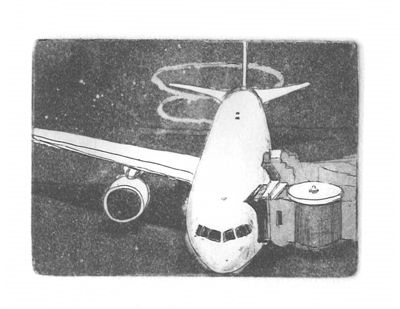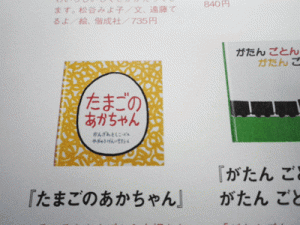「田原町のといしや」にて
地下鉄銀座線 田原町駅を出て、浅草レインボーホテルのほうへ歩いてすぐ。
「田原町のといしや」がある。
たくさんの砥石が、グレイ、ベージュなど、地味な色あいで並んでいる。無口な砥石も、これだけそろうと、なにか、語りかけてくるような。昔懐かしいガラス戸越しに、通りがかりのひとが、店内を覗き込む。
戸をあけて、鯔背な男が入ってきた。「彼は、とぎ師ですよ」と、砥石屋の主人が言った。
「ハサミをとがせたら、名人だ」
美容院などのハサミを、扱っているという。
「この間は、ヨーロッパで1000挺、といできましたよ。このごろは、包丁も頼まれるので、今日は、ソレ用の砥石を買いにきた」
「包丁は、ハサミ用の砥石でといでも、ダメだろ?」
「うん。光るけど、切れないね」
ふたりのやりとりを耳にしているうちに、私は、もうしばらく、この店に身
を置いて、ここで聞いた話を、お伝えしたいと思った。
(「ある砥石屋のものがたり」は11月23日スタートです)