『 a day in the life 』
『 a day in the life 』は、安西水丸さんが、14年間にわたり『チルチンびと』
〈結婚したばかりですぐに家を購入したりしたのも、
読んでいるうちに、井の頭公園に行ってみようと思った。
『 a day in the life 』は、安西水丸さんが、14年間にわたり『チルチンびと』
〈結婚したばかりですぐに家を購入したりしたのも、
読んでいるうちに、井の頭公園に行ってみようと思った。
4月4日が、「あんぱんの日」なんて、ご存じでしたか。
〈当時は「茶の子」といって大福餅や粟餅、
〈笑凹(えくぼ)
店であんぱんを買い、今日はよく売れたでしょう、
3月11日、午後3時から、西神田の風土社で「
「…… 最近、だんだんと若手の建築家で、
若手建築家部門最優秀賞・奥野崇さん・奥野崇建築設計事務所。
工務店設計者部門最優秀賞・野路敏之さん・(株)住まい工房。
工務店伝統型技能部門伝統技能賞・原淳さん・原建築。
を始め、16名の方々に賞が贈られた。そのつど、
続いて、懇親会。春のはじめの冷たい夜だったが、
……
第4回 チルチンびと住宅建築賞の作品、受賞の言葉、
あの日から、5年。
……
2011年3月11日、
……
悲劇は、ここから始まった。
『チルチンびと』87号では、〈東日本大震災・
……
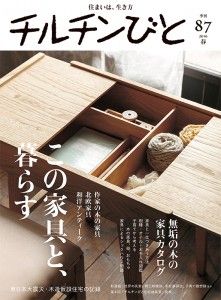
『チルチンびと』87号は、〈特集・この家具と、暮らす〉。3・
85歳の女性建築家、奥村まことさんが亡くなられて、一カ月。『チルチンびと』87号に、追悼のページがあり、田中敏溥さんも、こんな想い出をよせている。
……
ウェブ「チルチンびと広場」に連載の「奥村まことの方丈記」を楽しみにしていました。第1回〈新国立競技場・私案〉の最後の一文「常に建築家は護りの姿勢ではなく、前進しなければいけない。」は、強く心に残ります。まことさんは、強くてやさしい、大らかにして繊細な人でした。
……
「奥村まことの方丈記」は、コチラからごらんいただけます。
『チルチンびと』87号は、〈特集・この家具と、暮らす〉。山裾の家具工房から / この家にこの家具 / 子育てから考える 木の家具、木の家、木の道具 / 家具と一生つきあう方法 / 美しい木の家具カタログ / 東日本大震災・木造仮設住宅の記録- フクシマからのたより 2016 -孤独死を防げ。仮設からコミュニティデザインを問う-震災で問われた 木の家づくりのネットワーク - 届け、国にこの声が。大工力で国を動かし、つくった仮設 / 追悼・吉田桂二さん - 奥村まことさん / 第4回2015年度 チルチンびと住宅建築賞受賞者発表 ほか、充実の 256 ページ。定価 [本体917円 + 税]。3月11日発売です。
長田弘さんが、「机」について書いた文章が好きだ。(『感受性の領分』岩波書店)それは、こんなふうである。
……
机というのは、どんな家具とも、道具ともちがう。机はその机にむかう一人の日々のありようを黙って語っていて、ただ雑多としか見えないような机であれ、およそ整然としている机であれ、机上にあるすべてには、その机とともに暮らす一人の痕跡がのこっている。
そして、その最後は、こんなふうに終わっている。
机は、とどのつまり板子一枚だ。その板子一枚のうえには、一個の人生という、ごくありふれたものが載っている。
……
『チルチンびと』87号 の 〈特集・この家具と、暮らす〉の校正刷りを読んでいて、この文章を思い出した。写真は、編集部 某氏の机。校了の「痕跡」がのこっている。
『チルチンびと』86号 特集「火から始まる冬支度」にちなんで、ビブリオ・バトル― 暖かい冬のために。後篇。
……
Tさん。 〈このごろ朝が寒いので床の中で寝たままメリヤスのズボン下をはき、それから、すでに夜じゅう着たきりのシャツの上にもう一枚のシャツを、これも寝たままで着ることを発明して実行している。〉発明ですって。書いた人は、寺田寅彦。『柿の種』(岩波文庫)の ー 曙町より、から。ご存知、物理学者で、エッセイスト。少しあとには、この朝は頭が悪く、右の脚が、ズボン下の左脚に入ったりする、とかで、短い一本一本に、独特の味がある。
Sさん。 物理学者の目、といえば、『物理の散歩道』(岩波書店)も同じ流れ。ロゲルギストという7人のグループが、語り合う。たとえば、その3巻には、「防寒夜話」。〈寒い地方 ー 東北だったかな ー で、ハダカで寝るところがあるんだってね。もちろん、ごろ寝じゃない、ハダカでふとんにもぐりこむという意味だ。その方がねまきを着るよりあたたかいという……。〉で始まり、話は空気層に。そして、ハダカで寝ると本当に暖かいかを、論じる。これも、ユニークな味ですよ。
Uさん。 物理学者の目が続いたから、文学者の目も。『正弦曲線』(堀江敏幸・中央公論新社)に、「昼のパジャマ」という章があります。〈パジャマという衣装を夜にさえ身につけなくなって、もう三十年以上になる。昼寝は普段着のままがいちばん気持ちよいと思うので、パジャマどころか着替えも論外。夜は夜でいつの間にか寝ているというのが常態だから、 ……〉と読み続けるのを、遮るSさん。それ、面白そうだけど、今回のテーマは寝る話ではないからね。冬眠なら、いいけど。
……
『チルチンびと』86号 特集「火から始まる冬支度」は、12月11日発売です。お楽しみに。
『チルチンびと』86号特集 「火から始まる冬支度」にちなんで、ビブリオ・バトル― 暖かい冬のために。前篇。
……
Aさん。 高山なおみ『日々ごはん 12』(アノニマ・スタジオ)です。たとえば、12月のある日。〈朝ごはんは、「ルヴァン」のカンパーニュにゴーダチーズ(オレンジ色のけっこう熟成されたやつ)をのせて焼いた。これはまるで『ハイジ』の冬ごはん。ものすごーくおいしかった。〉冬ごはん、いいな。爽やかなエッセイの間にレシピ。たとえば、ある日の夜ごはんは、〈牡蠣酢、きりたんぽ鍋(比内地鶏、白滝、芹、ごぼう、長ねぎ、舞茸、きりたんぽ。〉と、読んで温まる。絶品。
Mさん。 鍋といえば、『江戸の味を食べたくなって』(池波正太郎・新潮文庫)。「二月、小鍋だて」の章。〈小鍋だてのよいところは、何でも簡単に、手ぎわよく、おいしく食べられることだ。そのかわり、食べるほうは一人か二人。三人となると、もはや気忙しい。〉そして、〈刺身にした後の鯛や白身の魚を強火で軽く焼き、豆腐やミツバと煮るのもよい。〉とある。ねっ、これも読んで温まる。こたえられませんよ。
D君。 鍋もいいですが、と『ヘミングウェイ短篇集 上』(谷口陸男編訳・岩波文庫)を取り出し、「二心ある大川」のページをを開く。〈彼は切株から斧で切り取った松の厚切りで火をたきつけた。その上に焼き網をかけ、四本の脚を靴で土の中に押しこむ。〉豆入りのポーク缶とスパゲティ缶をあけて、網にのせたフライパンにいれるんだね。食べる前に、男は、言うんだ。〈わかってるさ。こいつはまだ熱すぎる。〉これがいいんだ。
……
『チルチンびと』86号 特集「火から始まる冬支度」は12月11日発売です。お楽しみに。
『ぼくらの民主主義なんだぜ』(高橋源一郎著・朝日新書)が、ベストセラーである。『朝日新聞』の論壇時評を1冊にまとめたものだ。一回400字 ×5枚の時評の原稿を、1週間かかって書く、と著者インタビューで、語っていた。その内容の濃さはもちろんだが、タイトルのよさも人気の理由だろう。あとがきを読むと、ナット・ヘントフの『ぼくらの国なんだぜ』という小説から、とった、とある。
11月7日、雨。福井の住まい工房で、「チルチンびとMARKET」がひらかれた。“ 地域主義工務店の会 ” の名にふさわしく、地元の人気のショップが、多数出店。天然酵母のパ ンが、売り切れる。オーガニック・ランチボックスが品切れになる。インドの判子で布に模様を描くワークショップに、ひとが集まる。 地元の主婦、その家族、友達と連れだってくる若い人たち …… 来場者 は500人を超えた、という。来年もまた、各地で、「チルチンびとMARKET 」が、たのしく催されるはずだ。なぜって、それが、ぼくらの地域主義なんだぜ。
道後温泉から乗ったのが坊ちゃん列車
レトロなつくりで、のんびりとガタゴトガタゴト~☆
車内は木で装飾されていて
雰囲気がとってもよかったです♪
この坊っちゃん列車に乗ると
おまけで、松山にある「高島屋」の 大観覧車くるりんに
無料で乗せてもらえます♪
あいにくの曇り空でしたが、
天気が良いとかなり良い景色が期待できるので
お勧めです♪(*^_^*)
改めて坊ちゃんを読みながら
旅の思い出と重ねていきたいなと思った
amedioでした♪(*^_^*)