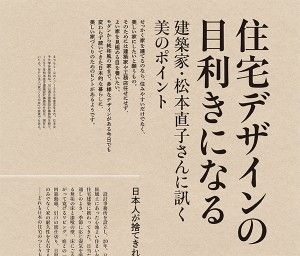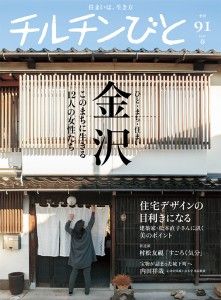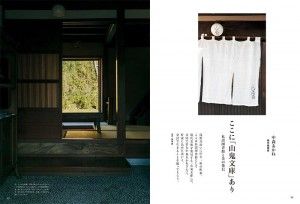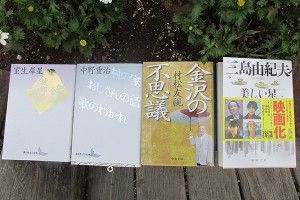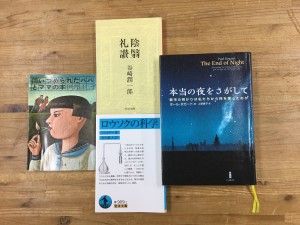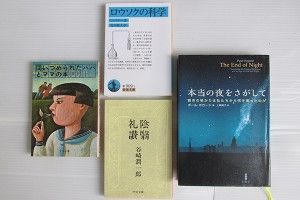住宅デザインの目利きになろう !松本直子
「住宅デインの目利きになる」には、どうしたらいいか。
建築家・松本直子さんのレッスンが、わかりやすく、楽しい。(『
1 “リビング・ダイニング” は切り離す
2 軒の下は特等席
3 キッチンづくりは、わがままに
………
そして、
10 惚れ惚れする天井に
まで、それぞれ、実例タップリに、教えてくれる。
このほか、
日本人が捨てきれなかった暮らしに美が宿る・松本直子 / 美しいリビングのための建具デザイン / 日本建築モダン化の系譜・三浦清史 / 吉田五十八「よい家」の極意 / 事例・伝統の日本美と西欧の暮らしが重なる家、
………
『チルチンびと』91号は、特集・金沢 ― ひと・まち・住まい。特集・住宅デザインの目利きになる ― 建築家・松本直子さんに訊く美のポイント。好評発売中 !