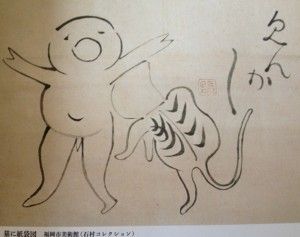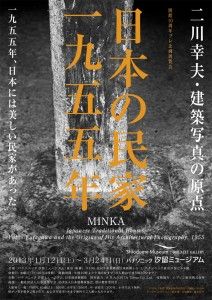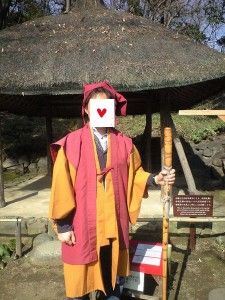昨年の秋におうかがいした「おいしい週末ライオン市」。食材、雑貨、植物、食堂・・・どれも魅力的なshopばかりが浅草の昭和初期築のライオンビルに集い、充実のイベントだった。主宰者の柴山ミカさんは、編集ライター兼プランニングディレクター。生来の食いしん坊と朝市めぐり好きが高じて、とうとう自分で食の市を企画運営するようになったという、素晴らしい行動力の持ち主なのだ。柴山さんの口から聞く市の話は、たとえとても小さな市でもなんだか面白そうに思えて、行ってみたくなる。この伝染力、逃すまじ! ぜひ市の魅力を伝えて欲しいとおねがいした。
その柴山さんから「朝市、一緒にいってみますか?」というお誘いがあり「行きます行きます」と二つ返事で、前から気になりつつ今回が初訪問という朝市に同行させてもらう。この日は、とある神社の朝市。土曜の朝九時。海辺の街に降り立てば、潮の香りが漂う。日差しがまぶしい。いつもの休日ならまだまだ寝ている時間のはずで、のっけから非日常な感じ。市には、採れたての野菜や海草、美味しい珈琲やさん、ドーナツやスコーン(あっというまに売り切れて食べそびれた)、手ぬぐいや雑貨が並び、青空の下、ついついお店の人とも会話は弾み、財布の紐も緩み、買い物袋はどんどん膨らむ・・・柴山さんは、さすが朝市の達人で、いつのまにか周辺の新たな市情報を仕入れたりしている。

お店の方からいろいろな話を引き出す柴山さん
たっぷり市巡りを堪能しても、まだ正午。そろそろお腹が空いてきた。「映画の観られるすごくいいカフェがあるんです。前に行った時は、映画に出てきたメニューを食べられて、野菜がすごく美味しくて・・・」と案内してもらったのは、 CINEMA AMIGO さん。静かな住宅街に、ガラス張りの木造りの建物が見えてきた。

CINEMA AMIGO外観。ワクワクさせる風情
ランチタイムはスクリーンは下りていないのだが、大きなスピーカーがあったり、いろんな形の椅子や机が全部、前方を向いているので、確かに映画館らしい。アンティークなムードの中に、赤い壁の喫煙室があったりして洒落ている。ランチを待つ間店内を探索しながら、ふと顔を上げると、キッチンカウンターに見覚えのあるスパイラルパーマの人が・・・なんと、3~4年前に定期的にお仕事をご一緒していたフードコーディネーターの上樂由美子さんがいるではないか!!! 一瞬目が合い、お互いしばらく絶句の後、「えーっ!!どうしてここに!?」と同時に叫ぶ。聞けば、2年ほど前に逗子に移住されたのだそう。こちらのシェフは日によって替わるのだが、たまたまこの日のデイリィシェフが上樂さんだった。すごい偶然! 呼ばれた! という感じ。

キッチンの中の上樂さん。変わらない頭部のシルエット
そういえば当時から都会に住みながら週末だけ田んぼを借りて農業をされていたり、アフリカで観た皆既日食の話をしてくれたり、ナチュラルでファンキーで素敵な人だったけれど、一層その雰囲気に磨きがかかって、すっかり逗子の住人になっていた。いまは広告の仕事を少しずつ減らし、レシピ提案、ケータリングやお料理教室にシフトしているんだそう。とても自然な流れだと思う。彼女のつくるご飯は、見た目が美しいだけじゃなくて心から満足のゆく味わいだ。
 バンズもお肉もしっかり真面目。ポテトは甘く、ピクルスのひとつひとつまで、絶品
バンズもお肉もしっかり真面目。ポテトは甘く、ピクルスのひとつひとつまで、絶品
地野菜のサラダ、デリ3種、蕪とセロリのポタージュ、キッシュ
映画のラインナップも、小粒ながらもキラリと光る良質の作品や、これは観ておいて! というこだわりが伝わってくるよう。映画だけじゃなく、上樂さんを含む「AMIGO KITCHEN」というフードクリエイター集団が交替でシェフを務め、映画に合わせたメニューを出したり、ライブイベントなど、ここはいろいろな人が集まってくる逗子の“情報発信基地”なのだ。プロデュースしているのは館長の長島源さん。すらりと長身で、穏やかな感じの方。スタッフの女性も、ジュリーアンドリュースみたいなワンピースを着ていて、スタッフ皆さんの雰囲気ごと、空間ぜんぶが映画みたい。ゆるゆると過したい休日にはぴったりの場所です。日田リベルテさんでも感じたけれど、大好きなミニシアターが次々に姿を消すのがさみしい昨今、地元愛に満ち、新しい文化を生み出すこんな映画館が、もっともっと増えてほしいなあと心から思う。
そろそろ帰ろうかと時計をみるとまだ14時過ぎ。これから帰ってもまだ一日はたっぷり残っている。なんて有意義な一日の過ごし方だろう。嬉しい再会もあり。早起きの甲斐がありました。朝市巡り、ハマりそう。そんな市の魅力をたっぷり教えてくれる、柴山ミカさんのコラムは、来月スタートです。どうぞお楽しみに。