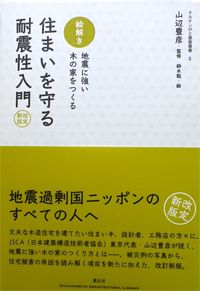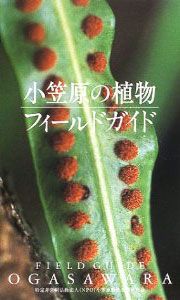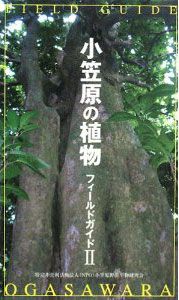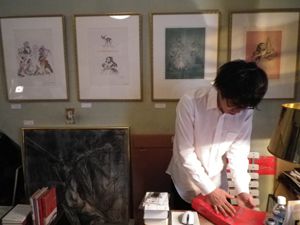商売の秘訣
JR・御茶ノ水駅、新宿よりの改札を出る。あれは、ナニ坂、というのかな。楽器屋さん、ファストフードの店、明治大学などを横目に歩くと、右正面に、三省堂が見える。小学生のころ、私は友達とつれだって、よく、三省堂へ、そして、東京堂へと本を買いにきた。左右の店は変わったが、この坂道を下る感覚は、今も昔も、変わらない。懐かしい。
三省堂が創業130年と知って、びっくりした。その歴史をたどる記事が『東京人』7月号にある。(『三省堂書店は小さな宇宙・木部与巴仁) 読んでいたら、こういう箇所に、目がとまった。それは —- 酒の飲めない者は酒屋に、飲める者は菓子屋に、という商売の秘訣がある。三省堂の創業者の方は、本が苦手だったから、書籍の仕事で成功したのだろうか、商売には、適度の客観性が必要かもしれない —- というところである。面白かった。
ちなみに、このブログを書く、アノヒトもコノヒトも、お菓子屋さんをやると、成功するような人たちばかりである。