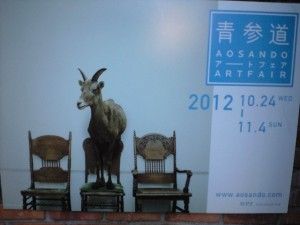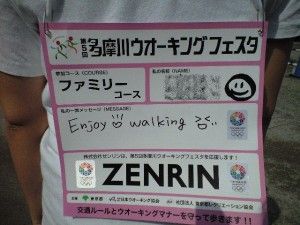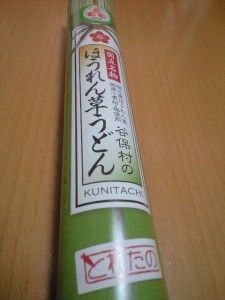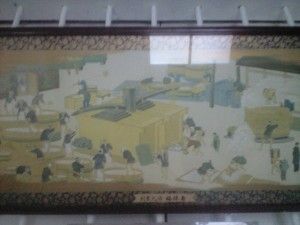慈慈の邸 さんで開催された「こうぼ食堂」ナヲさんの酵母料理教室「酵母と暮らそう」に参加してきました。
電車に揺られること2時間ちょっと、千葉県房総はいすみ市に到着。慈慈の邸はゆったりのびやかで美しく、いい気が流れていて心からくつろげる場所。玄関、キッチン、トイレ・・・多彩な左官や庭にも見どころがたくさん。眺めているだけでもあっというまに時間が過ぎます。

月曜の朝早くからお料理教室って、いったいどんな人が集まるの?と思っていましたが、大盛況。チルチンびと広場のツイッターを見て来てくださったという「手づくりや」さんは、埼玉よりなんと3時間以上かけていらしてました。勉強熱心!「月のとうふ」さんという地元在来種でつくるお豆腐屋さんや、君津で地元の野菜をつかった料理を出しているカフェの方、こうぼ食堂で市川ナヲ先生の魅力にはまってしまった方々・・・など、皆さん「こうぼ料理」に注目する方々ばかりで、自己紹介タイムからして面白かった。次に、食材となる大根を調達しに皆でブラウンズフィールドへ。

大きい~~。こんな大根相当時間がかかるだろうと思ったら、昆布酵母を入れて炊くと、あっというまに中までやわらかなるわ味もまろやかになるわ・・・恐るべし酵母!その他にも旬の柿やりんごの酵母、いったいどうやって使うの?という疑問を一発で解決してくれるレシピ5品。スタッフのスピッツさんがものすごく上手に炊いた香ばしい玄米といっしょに、いただきまーす!
噛めば噛むほどじんわりと身体に栄養がしみわたるような、滋養に満ちたごはんタイム。おなか一杯になります。

わかりやすく、常に生徒目線でお話ししてくれるナヲさんは、ナチュラルで少女みたいなほんわりした雰囲気。ここまで教えてくれちゃっていいの!?というぐらい丁寧に、酵母のABC、酵母の魅力を語りつくし、質問にもいつも+αな姿勢で熱心に答えてくれて、お人柄を慕ってやってくる人が多いのもうなずけます。

最後に、すぐに酵母生活がはじめられるように瓶と獲れたてキウイをお土産にいただきました。早速家に帰り、まずははじめのいっぽ。

この表面張力がだいじなポイントらしいです
酵母についてはまだまだ解明されていないことも多く、可能性がぐんぐん広がる。酵母って、愛いヤツ♪そんな風に思えてくる、朝9時半から午後3時までたっぷり充実の酵母教室。楽しかった!ナヲさん、慈慈の邸のみなさん、そしてお教室で一緒になった皆さま、どうもありがとうございました。
さらに嬉しいことに、「こうぼ食堂」の市川ナヲさんがチルチンびと広場でコラムをスタートしてくれることになりました!一人でも多くの方に、ナヲさんの魅力が伝わるとともに、酵母世界への扉が開くことを願って・・・スタート時期は追ってお知らせします。楽しみに待っていてくださいね~