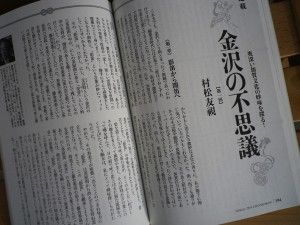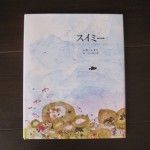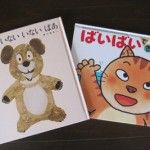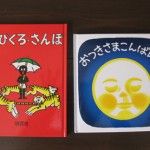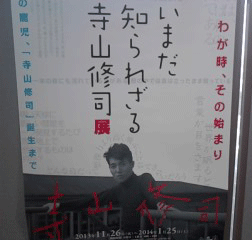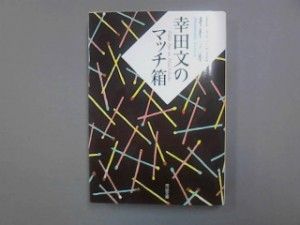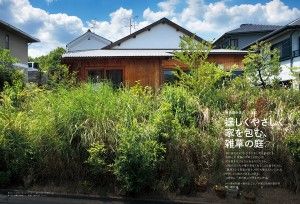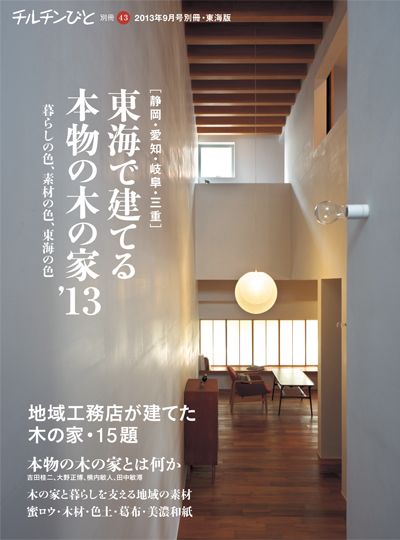先月、街巡りの途中でみつけたKARAIMOBOOKSさん。若いご夫婦と可愛らしいお嬢さん、家族3人のアットホームな雰囲気の店内に入ると、一番目立つところに水俣関連の本がずらり。他、九州関連本がずらり。石牟礼道子さんの本や原発、沖縄、ジェンダー論など社会派の本や雑誌、中南米関連の本も充実。いままで横目で通り過ぎていたところにまで視野が広がるような本棚だった。

店主の奥田順平さんに、自ら発行している「唐芋通信」をいただく。本で心の旅ができる、逃げたい、自由になりたいとき、本が希望になることを思い出させてくれる文章だった。凝ったデザインをせず、文字のみの“ザ・通信”らしさも潔い。「妻が書いたものの方がわかりやすいです」と、奥様の直美さんが西日本新聞に寄せたコラムもコピーしてくださった。なぜここ京都で、九州の人がサツマイモを呼ぶときの「カライモ」という名をあえて店につけたのか。また石牟礼道子さんや水俣との出会い、母としての思いなどが率直に綴られてほんとうにわかりやすかった。店の空気や文章から、誠実で、情熱があって、たくましくて優しい、そんなご夫婦の人柄が感じられた。
同じ週末、夫を連れてまた行った。ちょうどその時お店にいらしていたフォーラム福島の支配人、阿部泰宏さんを、奥田さんが紹介してくださった。ご家族が自主避難で京都住まいをされていて、数ヶ月に一度福島から会いに来るとき、よくここへ寄られる。福島の事故と水俣病を巡る問題には非常に似たものがあると感じて、ここで出会った本から先人に学んだり、奥田さんご家族と話をすることで救われる気持ちになったそうだ。「避難している身で遊びに出かけるのも気が引けるので、ここは貴重な娯楽の場所。気持ちが楽になる」と。
突然、外部から降りかかった災難から家族を守るため、大変な覚悟と決心で避難して、さらにそんな肩身の狭い思いをするなて。東京育ちの私は、その「外部」の一部には違いなく、思いがけず京都にやってきてのうのうと鴨川サイクリングを楽しんで、何を言っても説得力がない。と思ったけれど阿部さんは私のまとまりのない拙い意見もきちんと聞いてくださる。そして複雑な胸中を穏やかに、客観的に、率直にお話してくださった。毎朝目が覚めると明日はどうなるか不安に思う、その気持ちは皆同じはずなのに、強引な避難区域の線引きのために地元同士や家族内で、考え方の食い違いによる衝突や温度差が生まれる。闘う相手は身内じゃない。そういってとても心を痛めておられた。
『チルチンびと 77号』境野米子さんのコラムで、自主避難されている方を訪ねて京都に来られていたと知ったこと、震災前にお住まいを訪ねたことを話すと、「ここで境野さんの名前を聞けるとは!」と喜んでいただいた。なんと偶然、その後入ってこられたお客さんも福島の方で「やっぱりこの店にはなにかあるなぁ」と驚かれていた。私も、本屋さんでこんな出会いがあるとは思いもしなかったし、“カライモ”は私の両親の出身地、鹿児島の方言でもあり、不思議な縁を感じた。
+++++
P.S. 境野米子さんのブログに、ちょうどフォーラム福島で11月2日(土)から上映される「飯舘村 放射能と帰村」(土井敏邦監督)の試写会のことが書かれていた。阿部さんも、これは原発事故を扱った中でも、心の底から秀逸と思える1本です、とメッセージをくださった。
・・・「何よりも心が汚染されてしまったことが一番、悔しい」というひと言。
この言葉が最後にずしりと重く訴えかけてきます。
高低浅深の差こそあれ、福島県民みんなが抱えている思いです。
もし、ご覧になる機会があったらぜひ観てください。