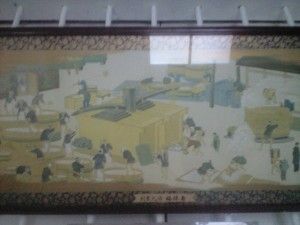先週は、古めかしい建物や雑居ビルの多いオフィス街にあるギャラリー2軒へ。
ひとつめはアールブリュットのインディペンデント・キュレーター、小出由紀子さんの事務所兼ギャラリー 。こちらでの展示はいつも何処かしら超越した作品が多く、想像を超える世界へ連れていってくれるので、今度はどんなのが出てくるかと毎回楽しみなのだ。今回のジーン・マン展「言葉の彼方」はDMの裏にある言葉につられて観に行った。
・・・ジーン・マンの描く顏には、反復されるひとつの顔が、そして無数の別々の顔が産みだされる以前の秘密を、それとなくあるいは力ずくで明かしているようなところがある。
(鈴木創士 「顔は一個の天体である―ジーン・マン展に寄せて」より)

粘土の壁からぬうっと出てきたような凸凹の顔がいくつも並ぶ。人間が、誰しも持っているがあまり人前では見せないし、自分でも意識せずに出た表情のような。ほんとにこんなだったら怖いけど。最初はわざわざ顔をつくろうと思ってたのではなくて、うわーっと盛り上げて積み重ねて、はっと気づいたら顔になってた・・・みたいな衝動的なコトだったような気もします。雲とか車の前面とか鯉の模様なんかが、どんどん人間の顔に見えてくる。そんなのにも似た、怖面白さがありました。12月21日(金)まで。
ふたつめは、アムコ カルチャー&ジャーニーさん。3Fのギャラリーアムコで開催されている伊賀の陶芸家・井崎智子さんの「びん展」が気になったのだ。びんというからにはガラスだろうと思いきや、イベント紹介文を見ると「ガラス瓶を集めて型を取り、山から掘り出した土を使って、薪窯でびんを焼き続ける・・・」とある。水虫の薬瓶や香水瓶、、ランプのカバーやラムネの瓶・・・などかつての生活用品だった瓶が、焼き物になると全然違った雰囲気になって不思議。形や、模様を再発見できる。

空気や灰に触れて、自然におきた反応で出た色は、なんとも神秘的で、びんの口とか曲線とか、くびれとかのところでまたさらに変化する様を見ているといつまで見ていても飽きない。井崎さんはもう、びんにはまってしまい、びんばっかり焼いているんだそうだ。作家さんのびんへの愛を感じる、面白くて可愛い展示です。12月25日(火)まで。

アムコさんの1Fでは「伊賀への旅」というテーマで月替わりで伊賀の作家さんを紹介する企画展を来年3月まで開催中。展示中の地域を特集した冊子『輪土』も制作・発行されています。
休日の馬喰町はとても静か。素敵なカフェやギャラリーもぽつぽつと点在していて、人ごみが苦手な方には穴場のくつろぎスポットです。