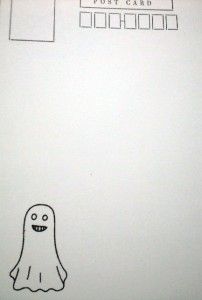スタンプ☆ポンポン
仕事の帰りに、品川で大好きなラーメンを食べ、のんびりと駅を散策していたら、
品川駅構内のエキュートにおもしろそうなものを発見☆
のぞいてみると、たくさんのスタンプが置かれていました。
ノートやハガキなどを購入すると、
自分でオリジナル作品を作れるらしいということで、
早速挑戦してみました☆
いざ、スタンプを押すとなると、ちょっと緊張。
ちゃんと思っている位置にきれいに押せますように!と
願いを込めてポン!!
スタンプの種類は100種類以上あり、
黒と赤(スタンプの絵柄によってきまっているけれど)の
2種類の色から選べます。
なんだか、ものすごくセンスを問われている感じ。
思い切り、ミスしてしまったものもあったけれど、
そこは、置いてある色鉛筆を駆使し、ごまかし成功(^_^)
真っ白なハガキがどんどん自分好みになっていくのは
なんとも楽しい時間でした☆
宛先欄にはお化けをポン
裏面は、オジサンと東京タワーを押して色鉛筆で帽子やワインをチョイ足し☆
自分で手を加えているだけに、愛着が増してしまいました…。
皆さんも機会があれば、是非お気に入りの一枚をつくってみてはいかがでしょうか。
amedi0 (前回書いた、F1話はまた今度。。。汗)