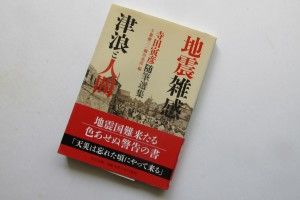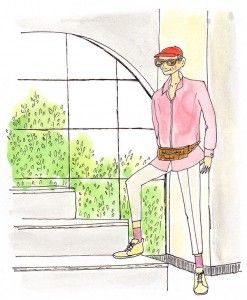人の集まる家のメニュー
『チルチンびと』 88号の「人の集まる家にしたかった」
〈……そこで、私は、客室の壁にメニューを書きだしておく。
例えばある正月。貼り出されたメニューは、山口さんの筆で、
生がきのカクテル フランス風 / カレーライス / かにの味噌汁 / ニシン漬 北海風 / 花咲がに / シュウマイ / チャアシユウ / まぐろ / たこ / かずのこ / 珈琲 コーヒー / アイスクリーム / 葛きり / 雑煮 / シチュー / 右ご遠慮なくお申しつけ下さい。
元日にいただくカレーライスは、とてもおいしかった。
…………
『チルチンびと』 88号 「特集・人の集まる家にしたかった」は、6月11日発売です。