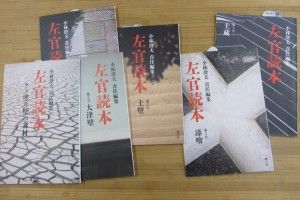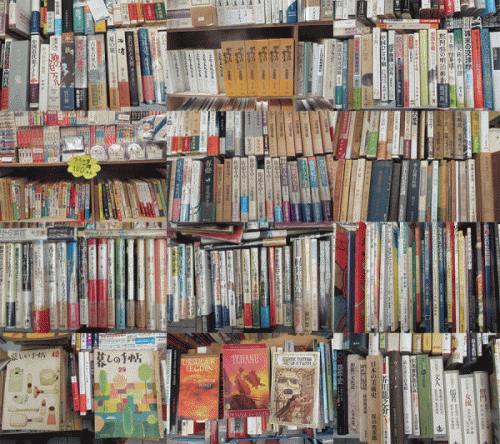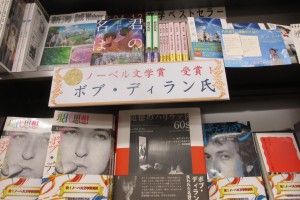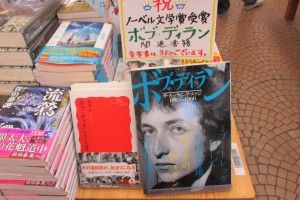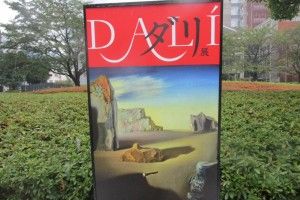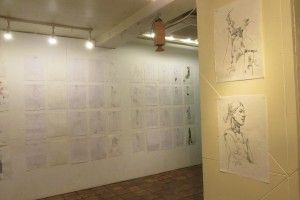サンキュー・ヴェリ・マッチ
『チルチンびと』冬号は「特集・灯をともし、薪を焚く暮らし」である。その企画の一つに「マッチ」にまつわるテーマがあり、村松友視さんのコメントが入る。取材に行く編集部のUさんに、ついて行った。
「かつて、マッチ・ポンプというコトバがあったよね」と、村松氏は言った。「自作自演みたいなことだったね。それから、マッチ一本火事のもと、と言って、冬の夜、町内を拍子木を叩きながら巡回していたよね。マッチのカゲが薄くなってしまって、ああいうセリフは、どうなってしまうんだろう」。そのほか、いろいろな話をした。「燐寸という漢字は、いいね」「マッチの火って、他の火にくらべると、カジュアルなカンジがするんだよね」「そういやあ、伊丹十三さんは、ベンラインのマッチが、世界一だと言ってたね」そして、当然、幸田文さんのマッチ(写真参照)の話も。
つぎからつぎへ、自在に言葉をくりだした。話は尽きず、サンキュー・ヴェリ・マッチだった。話の終わり頃、彼は言った。「しかし、昔は、いつもこんな話ばかりしていたよね」そうだった。暇があれば、コーヒーを飲んで、言葉のキャッチボールを繰り返し 、飽きるということがなかった。あれは、贅沢な時間だったと、つくづく懐かしい。
………
『チルチンびと』冬号は、12月10日(土)発売です。お楽しみに。