先人の知恵を守り継ぐ-森野旧薬園と大宇陀を訪ねて

身近な薬草を育む里山は
人と自然がつながる場
賽郭が育った薬の里、大宇陀の山に入りたくなった。ちょうど今は薬日にあたる旧暦5月5日に近い。いつもお世話になっている大宇陀観光協会会長で植物にも詳しい藤本まさやさんにお願いしたところ、ツルニンジン採りにご案内してくださるという。この夏、関東から大宇陀に移住することになった知人の佐藤さんご一家もお誘いして、森野旧薬園から車で10分ほどの山に入ることにした。ツルニンジンの根は滋養強壮などにいいという。薬草を漬け込む薬酒づくりが好きで、知人から教えてもらって以来、ツルニンジンの根も採るようになった藤本さん。小さくて3年もの、大きくて10年もの。根を傷つけないように掘るのはなかなか難しい。目が慣れてくると次々に発見でき、30分余りで10個ほど収穫できた。夕方、囲炉裏のある徳源寺で山菜鍋をしようということになり、そばに生えていたヨモギやフキも採取。寺に向かう途中、藤本邸の裏の空地でセリを採ったり、寺の境内に群生するミツバを採るうちに、けっこうな量になった。大宇陀育ちの鶏「宇陀味どり」を入れた山菜鍋だ。ツルニンジンの根は、薬酒のほか、スライスして蜂蜜をつけた刺身でもいい。藤本さんご自慢の薬酒をいただきつつ、贅沢な宴となった。


思い立ったらすぐに採れる、身近な山野草が与えてくれる恵み。天地の気に満ちた植物の力。たとえば本来、春の七草や新年の門松は、屋敷内や畑の畝ではなく、近くの山野で採取することに意義があった。より原初のエネルギー、山の神に近い力を取り入れる意味があったのだろう。
しかしその山野は、人の手が適度に入った里山であった。人の手がまったく入らない荒野では、植生遷移の途中相で育つ植物は絶えてしまう。かつて日本人にとって田畑に次いで 大切な場であった「家の裏山」。水、 薪、堆肥、山菜、薬草、椎茸の原木 栽培など、生活必需品の至近の供給 源であり、自然と人間の生活空間を つなぐ境界域でもあった。そして裏 山の遥か向こうは、手つかずの奥山 がある聖域だ。東北では、裏山のな い平地では、近くの木や山菜を屋敷 内の一画に移植し、屋敷林として里 山を再現することもあった。会津地 方では、屋敷に再現した山を坪山と よび、神が遊ばれる清い場なので汚 さないという言い伝えもあるという。 最も身近な自然、里山は、家族の守 護神が座す場なのだ。

自生植物ならではの香味に、ツミレや大宇陀産鶏肉のコクが相まっ
て実に美味。自然に囲まれた徳源寺の囲炉裏端で贅沢なひととき。





































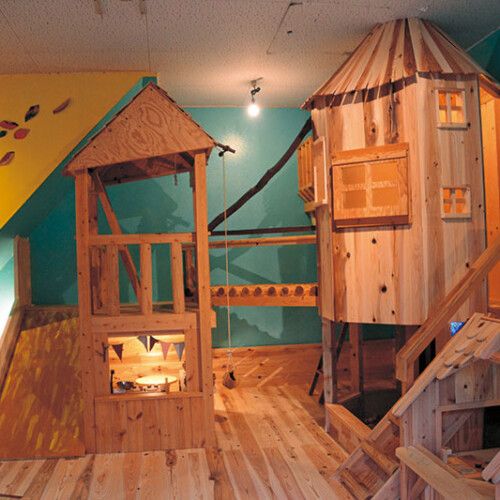
この記事へのコメントはありません。