
泉さん自邸のリビングの天井は現しとなった杉の太鼓梁と、連続した垂木から成る。 職人の手仕事による美しい仕口も目を引く。 (写真=相原 功)
かつて住まいの中で当たり前に目にしていた梁が、
いつの間にか遠い存在になっている。
けれども、天井が現しになり立派な梁や木組が見える空間には、
なぜだか住まい手をほっとさせてくれる力があるようだ。
全体のバランス、素材やディテールを重視する
建築家・泉幸甫の考える「梁の美学」とは。
文=泉幸甫
人間は率直で真摯なものにあこがれる。逆に、オブラートに包んだような言い方や、あたかも本物のように見せたフェイクを嫌う。それでは、率直であればいいのだろうか。率直であることは、実はなかなか大変なことだ。偽物より本物のほうがいいのは当たり前だが、世の中なかなかそうはいかないからこそ、人間は率直さ、真摯さにあこがれる。このことが、柱や梁を現しにした木造建築が好まれる本質であるのではないだろうか。
天井を剥がすと梁が現れるが、何故わざわざ天井を張って、その中身を見えなくしてしまったのか? それは、天井を張ることで断熱効果を上げることができるし、天井の中には電気の配線、換気扇のダクトなどが這いずり回っているので、いろいろなものの目隠しに役立つからだ。また何と言っても、中が見えないからいろいろなことを考えず、雑に仕事をすることができる。
ところが、梁を見せるとなると、先に書いたようなことに対して一つひとつ配慮をしなければならない。まず、丸見えになってしまう構造の材質を日本の松、杉、あるいは輸入材のベイマツなどから選択する。それは予算にかかわることでもあるし、仕上げ方をどうするか、また見えるとなれば美しく見えるように、梁や根太の架け方を考える必要がある。さらに、それらを緊結する金物も見えないようにしなければならない、などなど。そんなこんなで、結局のところ、設計者やつくり手には相当のやる気と技術が求められることになる。
しかし、見られるからと言って、技巧的に妙にきれいにすることにこだわりすぎると、それもいやなものになる。誠実に、きちっとした仕事になっていればそれでよい。それは人柄を見るようで、梁を見せるということは人柄をもろに見せているようなものかもしれない。案外奥深い世界なのだ。
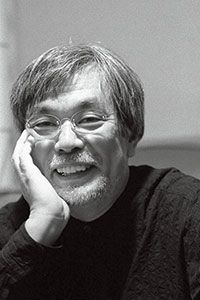 泉幸甫
泉幸甫
1947年熊本県生まれ。日本大学修士課程、千葉大学博士課程を修了(工学博士)。泉幸甫建築研究所を設立し、建築作品をつくりながら、日本大学教授も務める。また住宅設計を学ぶ人のための「家づくり学校」の校長として後進を育てている。

この記事へのコメントはありません。