祖父母と孫のフォークロア

親子2世帯が同居を考える際に、
大きな理由の一つとなるキーワードは「子育て」。
祖父母は孫を慈しみ、孫は祖父母を慕い、
その絆は親子間のそれよりも、強いことがあります。
両者の間には何があるのかを、民俗学的にひもときました。
文、写真=近藤夏織子
祖父母と子どもの間には
特別な交歓がある
「子どもの頃、お祖母さん、お祖父さんが教えてくれたことは、今でもよお覚えてる」。
古老の口から語られる、時を超えた古き声。大勢の古老への聞き取りをさせていただくなかで最も心の深層に響くのは、彼らの祖父母の話だ。
古老たちの遠い記憶に細胞が共鳴するのか、神秘的ななにかが心に浸透していくのを感じる。この透明な感覚の彼方に呼び起こされるのは、生きていたらちょうど100歳になっていたであろう、今は亡き田舎の祖母の姿。そして古老の昔話が極まったとき私の心の奥から子ども時代の感覚が蘇ってくるのだ。
目の前の古老を通して、田舎の亡き祖母が語りかけてくれているような不思議な感覚。さらに言うならば、亡き祖母を超えて、神仏からのメッセージのように感じられるときすらある。そんなときは取材メモを取る手が止まり、ただその場の体験を全身全霊で吸収しようとする、子どものような私がいる。
この不思議な感覚から確信できることがある。時として、祖父母と子どもの間には、霊的な交歓がなされているのだ、と。
唄や語りが孕む
伝承の力
かつての農村では、小さな子どもたちの見守り役は決まって祖父母であった。若夫婦はそろって田畑の重労働に出かけるので、小さな子どもは祖父母に預けるしかない。隠居したとはいえ、祖父母にもそれなりの畑仕事があり、筵や菰、縄や草履などをつくる藁仕事、織物にまつわる仕事もある。そこで、仕事をしながらの子守になるわけだが、そこで力を発揮したのは、唄や語りであった。
大和高原で育った今の80歳代以上の古老は、実に唄に長けている。音程の正しさなどという観点から得手というのではなく、とにかくその方独自の味がある。山間に生まれ、大地を這うようにして田畑を耕してきた古老たち。その語りには、謡いのような抑揚があり、なによりも大地の気が漂う滋味がある。
物心つかない子どもにとって、この響きで語られる昔話は、異次元へと誘ってくれる体験そのものになる。ましてやテレビもラジオもない時代、古老の昔話は一種の霊力すら放散していたことだろう。
現実社会を生きるための技を子に伝える親に対して、祖父母には、生きるための力を孫に授ける役割があったのではないだろうか。
祖父母から孫へと
受け継がれるもの
幼少時、祖母から昔話と唄を聴いて育ったという岩手県遠野市の語り部、阿部ヤエさんは「子どもを唄で育てることは、生まれたら人間らしく生きるために必要な力を起こしてやり、2歳、3歳と起こした力を基にして唄で遊んでやる。そしたら子どもが唄で遊んで生きる力を身につける」*という。つまり唄には、子どもの成長に合わせた「生きる力」を芽生えさせ、育てていく作用があるのだ。
さらに「唄は精神育てだから、(生まれて)何カ月頃にはこの遊びができれば大丈夫」というタイミングも伝わっていて、何よりも「気持ちと体、そして人の心が育つことが大事」と語っている。
また、沖縄の久高島では、島で生まれた女性は、家や村の祭祀をとり仕切る神女としての役割を果たす。女性たちが神女になるために、かつて12年に一度行われていたイザイホーという成巫儀式があった。そこではまず神女としての霊力を授かるために祖母から神名を受け継ぐ。親ではなく祖母から隔世継承することで、一直線ではなく、入れ子式、二重螺旋状に霊力が伝わっていったわけだ。しかもそれは幼少時の体験を「思い出す」年齢を経て、生き生きと活性化されるのだ。
何十年か後、思い出されたこの体験が
芽を出し、孫世代に語られるときがくるだろう。
そして孫の孫の孫、七代先まで心は伝わっていく。
文字による記録と
体験による伝承
祖母と過ごした幼少時の体験が、人生において多次元にわたる深い感覚を生み出していることに私がようやく気づき始めたのは、40歳を超えてからだろうか。私の場合、率先して農作業を手伝うわけでもなく、祖母の地味な作業を、ただそばで見ていたことが多かった。今になってようやく、それがとても特別な時間であり、時空を超える鍵となる体験であることが痛感できる。
しかしその記憶はあまりにも断片的だ。現代は、長きにわたって古き智慧の継承が絶えかけている、特異な時代である。二重螺旋の縄目がほどかれた今、私たちは今までにない新しいやり方で、継承を紡ぎ直さなくてはいけないのかもしれない。
最近感じているのは、ライフワークとして続けている古老への聞き取りが、継承体験としての可能性を有しているのではないかということだ。聞き取りの現場はいつも感動に満ちていて、10年以上前にお伺いした話が、幼少時の記憶のように突然蘇ることがある。その直感がきっかけとなり導かれるようにして、次なる出会いと感動につながっていく。伝承には、文字による記録と、体験的な記憶があるが、後者こそが本来の伝承であると断言したい。
ほどかれた絆を結び直し
未来へつなぐ
しかし悲しいかな、この10年間で、何人の古老たちが旅立ってしまったことだろう。急がなくてはいけない。あと何年、自給自足時代の体験者たちに聞き取りができるだろう。その危機感が決意させたのが、昨年末の大和高原民俗文化研究団の結成だった。研究団といっても、学究的なメンバーが集まっているわけではなく、実質、何の規則もない。ただ私の聞き取り取材に同行を希望される方、そして身近な古老たちへの聞き取りを希望される方が入ってくださっている。
研究団という看板を掲げているものの、めざしているのは、古老たちとの心の交流だ。聞き取りの現場では、古老たちの話が深まるにつれ、感動して思わず涙ぐむ若いメンバーもいる。きっと何十年か後、思い出されたこの体験が芽を出し、孫世代に語られるときがくるだろう。
ほどかれた絆を新しく編み直す作業は、とても小さく地味な作業の連続である。しかしその源には、大いなる生命の胎動がある。
心を開き、心で語ろう。
そこからきっと心は伝わっていく。
孫の孫の孫、七代先へ。
*佐藤一子「文化創造的営為としての昔話の口承活動」
近藤夏織子(こんどう・なおこ)
医学書出版社に在籍後、フリーに。大和高原に暮らしながら、民俗学を中心にノンジャンルの取材と執筆活動、音楽活動を行う。「webチルチンびと広場」で「七代先につなげたい、先人の心」を連載中。

































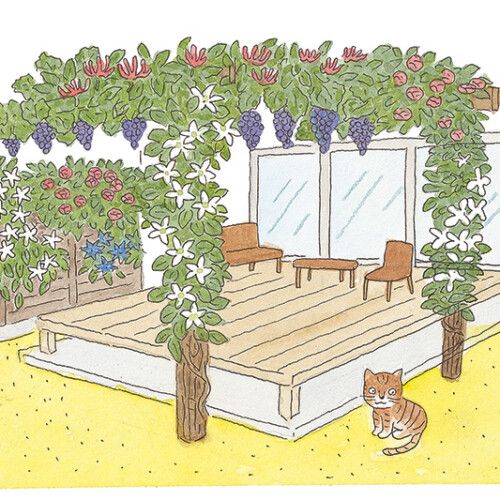




この記事へのコメントはありません。