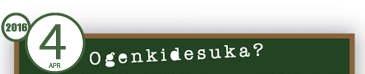曽根 康男
そね やすお
自然観察指導員、ネイチャーゲーム指導員、インタープリター、プロジェクト・ワイルドエデュケーターとして活動中。エコミュージアム、インタープリテーション、民俗学に興味あり。
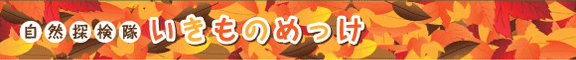
![]()
オトシブミの落とし文
初夏。雑木林のお散歩が楽しい季節です。
新緑、草木の花、野鳥のさえずり・・・ 楽しみはたくさんあるのですが、今回紹介させていただくのはオトシブミという昆虫。大きいものでも1センチに満たない甲虫で、日本には20種類以上が生息するのですが、幼虫のために植物の葉を丸めて揺籃(ようらん・ゆりかご)を作るというおもしろい生態を持っています。
種類によって揺籃の形は違うのですが、基本的な作り方としてはまず葉っぱに切れ目を入れ、端から巻いていく途中に卵を産みます。ただ巻くだけだとほどけてしまうので、途中で葉の一部を折り返してかぶせたりたるんだ部分を包みこんだりしながらきっちりと仕上げていきます。写真はヒメクロオトシブミがつくった揺籃で、仕上げた揺籃を切り落とすオトシブミも多く、地面に落ちた揺籃を巻紙の手紙に見立てて「落とし文」と呼ばれるのですが、ヒメクロオトシブミの揺籃は写真のように葉っぱに残ったままのものがよく見られます。
卵から孵化した幼虫は巻かれた葉っぱを食べて成長し、揺籃の中でさなぎになり、羽化すると揺籃を食い破って出てきます。つまり穴の開いてない「落とし文」を見つけたら、持ち帰って小瓶にでも入れておけばやがて成虫がでてくるというわけで、幼虫の飼育の容易さではナンバーワンかもしれません。
オトシブミの仲間はちょっと注意して探せば街なかの公園などでも見つかる身近な昆虫で、ゴールデンウィークから梅雨入り前くらいまでが産卵期。さあ、「落とし文」を探してみましょう!