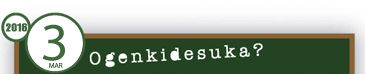曽根 康男
そね やすお
自然観察指導員、ネイチャーゲーム指導員、インタープリター、プロジェクト・ワイルドエデュケーターとして活動中。エコミュージアム、インタープリテーション、民俗学に興味あり。
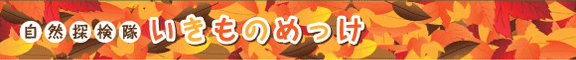
![]()
桜咲く
各地から桜開花の知らせが届く季節となりました。
県や市・町それぞれに標準木というのを定めており、その木の芽やつぼみの様子から「あと何日で開花」とか「咲きました」とか「三分咲き」とか「満開」とか発表するのですが、その標準木の多くはソメイヨシノ(染井吉野)という桜の品種です。校庭や公園などで一番よく目にする桜なのですが、じつはこのソメイヨシノ、江戸時代末期に江戸の染井村(現在の東京都豊島区駒込)の植木屋が売り出したと伝えられています。その植木屋がどこかで偶然見つけてきて売り出したのか、それとも誰かがかけ合わせで作り出したのかははっきり分かっていないのですが、ひとつひとつの花が大きく、花付きもよくて見た目が豪華。成長が早くて10年も経てば立派な木になり、他の桜に比較すると若いうちから花を咲かせる・・・などの理由から、明治以降全国の城跡や公園、学校、道路沿いなどに植えられ、急速に普及していったということのようです。
ではもともと日本に自生していた桜は・・・というと、ヤマザクラやオオシマザクラ、エドヒガンなど9種類(11種類という説もあります)の野生種があり、それにこれらの変種や交雑種(自然交雑もあれば人が交雑させたものもあります)を加えると現在400以上の品種があるといわれています。
さらに「根尾谷の淡墨桜(岐阜県)」、「三春滝桜(福島県)」、「石割桜(奈良県)」などのように個々に名前を付けられた桜もあり、日本人って古来から桜が好きだったんだなぁと思わせますね。
いつか、桜前線を追いかけながら南から北へのんびり旅してみたいものです。