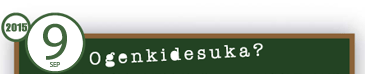曽根 康男
そね やすお
自然観察指導員、ネイチャーゲーム指導員、インタープリター、プロジェクト・ワイルドエデュケーターとして活動中。エコミュージアム、インタープリテーション、民俗学に興味あり。
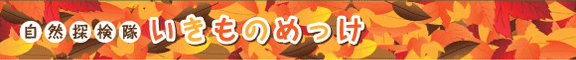
![]()
秋、到来
9月。南北に長い日本列島ではまだ夏のところもあれば、野山はもうすっかり秋の装いというところもあると思いますが、気象庁では9、10、11月を「秋」としているので、とにもかくにも日本中が秋です。
秋の花といえばハギやらススキやらオミナエシやら・・・いわゆる秋の七草が頭に浮かびますが、今年の秋の花、全体的に開花が早いようです。特に顕著なのが、秋の七草ではありませんがヒガンバナで、お彼岸の頃に咲くから「彼岸花」なのに、西日本や九州のあちこちで8月下旬から花が確認されています。
これは夏に猛暑日が続いたことと関連があります。植物の生理には日長(一日のうちの昼間の長さ)と気温または地温が大きな影響を及ぼしているのですが、夏の間球根の形で地中にいるヒガンバナにとっては地温の変化が花を咲かせる大きな要因になっています。ざっくり言うと猛暑日が続いた後に急に涼しくなって地温が下がると「やばい、もう秋か!?」と焦ったヒガンバナが、日長はまだ夏のままなのにあわてて芽を出し、茎を伸ばして花を咲かせる・・・ということです。
ちなみに秋の七草については万葉集で山上憶良が「秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ) の花 萩の花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝貌(あさがお)の花」と詠んでいますが、このなかに彼岸花が詠みこまれていないのは、ヒガンバナは中国大陸が原産の外来種で、奈良時代にはまだ日本には伝わっていなかったから・・・だそうですよ。