自転車を漕ぐ
 山口瞳は色紙に「自転車を漕ぐというのはおかしいと吉野秀雄先生が言った」と書くことがあった。吉野先生は日本を代表する歌人で万葉集の研究家でもあった。若かりし頃、鎌倉アカデミアに学んだ瞳は吉野先生の薫陶を受けることになる。正しい日本語を学んでいる吉野先生は漕ぐというのは櫓を漕ぐというように前後運動、あるいは上下運動を指す言葉であり、回転運動である自転車のペダルを回す動きを表現するのには適さない、とお考えだったのだろう。さんずいというところも陸上のものである自転車にそぐわない。
山口瞳は色紙に「自転車を漕ぐというのはおかしいと吉野秀雄先生が言った」と書くことがあった。吉野先生は日本を代表する歌人で万葉集の研究家でもあった。若かりし頃、鎌倉アカデミアに学んだ瞳は吉野先生の薫陶を受けることになる。正しい日本語を学んでいる吉野先生は漕ぐというのは櫓を漕ぐというように前後運動、あるいは上下運動を指す言葉であり、回転運動である自転車のペダルを回す動きを表現するのには適さない、とお考えだったのだろう。さんずいというところも陸上のものである自転車にそぐわない。
また、これも日本語に敏感な瞳だから、授業中の先生の言葉を憶えていたのだろう。
僕は長いこと自転車に乗れなかった。生家の前が繁華な都電通りだったので、祖母が危ないからといって許してくれなかったのだ。 …
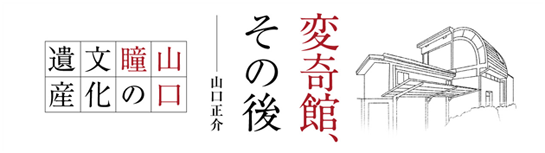
 が亡くなる数カ月前の十二月ごろだったか、庭に鶏卵大の黄色いものが落ちているのに気がついた。何だろうと思ったが、思いつくものがない。間近で見ると、それは何かの果実であり、夏みかんのごときものであった。もしかしたら鳥が運んできて、ここで落したのだろうか。そう考えながら、頭上を見上げてみると、そこには柚子の木が枝を延ばしていた。そして、枝先に数個の果実が実っている。
が亡くなる数カ月前の十二月ごろだったか、庭に鶏卵大の黄色いものが落ちているのに気がついた。何だろうと思ったが、思いつくものがない。間近で見ると、それは何かの果実であり、夏みかんのごときものであった。もしかしたら鳥が運んできて、ここで落したのだろうか。そう考えながら、頭上を見上げてみると、そこには柚子の木が枝を延ばしていた。そして、枝先に数個の果実が実っている。 斎の模様替えを終えて、仕事が捗るようになった。とはいえ、だからといって一生懸命、仕事をする訳ではない。何かと雑用を思いつき、そうだあれをやらなければ、などと考えている。
斎の模様替えを終えて、仕事が捗るようになった。とはいえ、だからといって一生懸命、仕事をする訳ではない。何かと雑用を思いつき、そうだあれをやらなければ、などと考えている。 年に一度、部屋の模様替えをしたくなる。
年に一度、部屋の模様替えをしたくなる。 イトルに惹かれてNHKのBSで放映された「カールさんとティーナさんの古民家村だより」を観た。ここには、僕が理想とする住まいの姿があった。新潟の寒村で、打ち捨てられ、朽ち果てた古い家屋の再生に挑む。とはいえ、ドイツ人である建築家、カールさんの古民家再生は通常とは少し違っている。
イトルに惹かれてNHKのBSで放映された「カールさんとティーナさんの古民家村だより」を観た。ここには、僕が理想とする住まいの姿があった。新潟の寒村で、打ち捨てられ、朽ち果てた古い家屋の再生に挑む。とはいえ、ドイツ人である建築家、カールさんの古民家再生は通常とは少し違っている。 近、知り合いの若い女性庭師に訊いたら「フィカス・プミラは悪魔の植物。未だに花屋で売られているのが信じられない」とのことだった。
近、知り合いの若い女性庭師に訊いたら「フィカス・プミラは悪魔の植物。未だに花屋で売られているのが信じられない」とのことだった。 が家の南隣りのお宅が増築することになったことは、ちょっと前に書いた。その増築部分は我が家ともっとも隣接する場所だった。
が家の南隣りのお宅が増築することになったことは、ちょっと前に書いた。その増築部分は我が家ともっとも隣接する場所だった。 が町のゴミ収集は分別方式で有料(ごみ袋を買う)である。
が町のゴミ収集は分別方式で有料(ごみ袋を買う)である。 が家の東側に私道を隔てて二階建てのアパートがあったが、取り壊されて売り土地という立て看板が建てられているということは、すでに書いている。
が家の東側に私道を隔てて二階建てのアパートがあったが、取り壊されて売り土地という立て看板が建てられているということは、すでに書いている。 道を隔てた東側にあった二階建てのアパートが無人になり、しばらくそのままになっていたが、取り壊されて更地になり、売物件という大きな看板が建てられた。東側から、変奇館の全容を眺められることは、これまでなかった。こんな機会は滅多にあるものではない。僕はさっそくデジタル・カメラを手にすると、はじめて距離を隔てて眺めた変奇館を撮影した。実は、西側のアパートが取り壊されて更地になったときも変奇館の西側を、充分な余裕をとって撮影してある。
道を隔てた東側にあった二階建てのアパートが無人になり、しばらくそのままになっていたが、取り壊されて更地になり、売物件という大きな看板が建てられた。東側から、変奇館の全容を眺められることは、これまでなかった。こんな機会は滅多にあるものではない。僕はさっそくデジタル・カメラを手にすると、はじめて距離を隔てて眺めた変奇館を撮影した。実は、西側のアパートが取り壊されて更地になったときも変奇館の西側を、充分な余裕をとって撮影してある。