近年、我が国では伝統的な日本建築が激減し、杉はその本来の用途を失い、今では「世界の木材の中で最も安い材ではないか」とすら囁かれています。
コストダウンの努力は当然ですが、ここまで価格が下がってくるとかなりドラスティックに下げなければなりません。その結果、以前ご紹介したハーベスタやフォワーダ等を駆使した新たなシステムに取り組みました。しかしこのシステム、機械代だけで数千万円に上ります。これを使って搬出される杉の価格がどんどん下がっている中でのこの出費は、経営者としてはかなり度胸の要る決断です。中古の機械を組み合わせるなど、コストをできるだけ抑えて導入にこぎつけました。
しかし人間がいません。ここは「限界集落」です。よって外部、それも全国に向けて、ネットやハローワークで求人情報を流します。毎年開催してきた森林環境プログラムを通じ、「森林を守りたいと考えている市民は意外と多い」と認識していましたが、応募者は少数。当地まで面接を受けに来て、「あまりにも田舎」「あまりにもなにもない山の中」に驚いて帰ってしまう人もいます。今年の春、2名の新入社員を受け入れましたが、募集開始から2年かかりました。
こうした外部からやってくる「新規参入者」達は、限界集落に住む人々の生活を支えることにもなります。国も通称「みどりの雇用」という制度で、年間数十日講習会を開催。これを3年間通して受講すると、林業で必要な免許や資格のほとんどが取得することが出来ます。しかし最も大切なのは「安全」です。不安定な傾斜地で1本数100kgの杉の木を伐り倒す、あるいは巨大な機械を操作するのですから、命がけの仕事です。仕事の要領は勿論、服装も非常に重要です。森を愛し、森を守るために集まってくる若者たち、仕事の環境が安全であることは当然ですが、なんといってもカッコよくなきゃいけません。
次回は安全でカッコイイ林業についてお話しましょう。

中津江村の最盛期の人口は7000人だったそうですが、私が帰って来た昭和60年当時は1700人でした。その後、20年で1300人前後になりましたが、「今年は1人増加」など微増する年もあって、「しばらくはこの位の人口で推移するのかな」とちょっと安心していました。しかし平成17年3月、中津江村は日田市と合併し、あっという間に人口は1000人を切り、いよいよ限界集落となりました。合併すれば中津江村役場は消滅しますが、そもそも役場こそが「最大の雇用の場」だったのですから、こうなるのは当り前です。「平成の大合併」と言われたあの時期、国の脅しにも見えた勧奨には理由が合ったのでしょうが、山の中の小さな村にとって、結果は目を覆うばかりです。

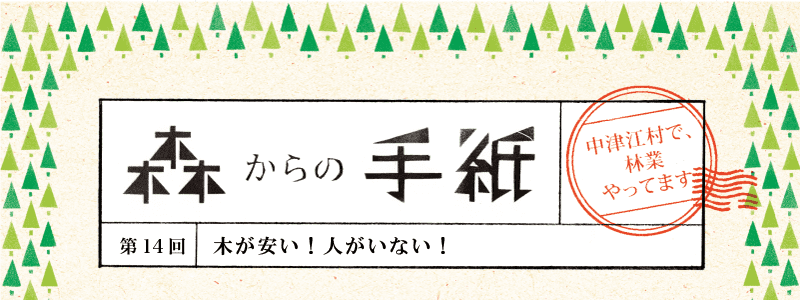

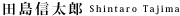
 田島山業株式会社 代表取締役/大分県林業経営者協会理事/(社)九州経済連合会九州次世代林業研究会委員/日田林業500年を考える会会長
1980年慶応義塾大学法学部卒。西武セゾングループ代表室勤務を経て、1988年、父、祖父の急逝に伴い、家業を継ぎ林業経営者となる。日田林業500年目にあたる1991年、子どもたちを対象とした森林環境教育、また学生、社会人の森林ボランティア受入れを開始。「断固森林を守る」取り組みを続けている。
田島山業株式会社 代表取締役/大分県林業経営者協会理事/(社)九州経済連合会九州次世代林業研究会委員/日田林業500年を考える会会長
1980年慶応義塾大学法学部卒。西武セゾングループ代表室勤務を経て、1988年、父、祖父の急逝に伴い、家業を継ぎ林業経営者となる。日田林業500年目にあたる1991年、子どもたちを対象とした森林環境教育、また学生、社会人の森林ボランティア受入れを開始。「断固森林を守る」取り組みを続けている。