第10回の「健康な森のサイクル」(林野庁資料)という図を思い出して下さい。これは「木を植え、育てる」という行為が一方で環境を守り、とくに地球温暖化防止に大いに役立っているということを示しています。しかし環境を守っていることは直接収入にはなりません。収入を得る為には、木を伐らなければなりません。それでは、木はいつ伐ればよいのでしょう?
各県で主要な樹種に伐採の目安となる「標準伐期齢」というものがあります。老木でも毎年少しずつ成長しますが、やはり若い木の方がどんどん成長します。「木の成長が鈍化する頃に伐採し、新たに植林する…これを繰り返すと収穫量が最大になる。木の成長は地域によって異なるので、現に伐採されている林齢も考慮に入れている」ということだと思います。

大分県の標準伐期齢は、昔から変わらず杉35年、ヒノキ40年となっています。今から15年前、多くの杉の木が35年生になりました。電柱にちょうど良いサイズです。しかし既に、木の電柱の需要はありませんでした。
杉やヒノキ等の「国産材」の価格は昭和55年をピークにひたすら下がり続けています。それは外国産の木材にどんどんシェアを奪われてきたことを意味しますが、その間1ドルが250円から80円まで円高に振れたのですから、非常に不利な戦いを強いられてきたと言えます。一方、輸入された木材は主に天然林から産出された直径1mを超す巨木も多く、「35年生のサイズではとても太刀打ちできない」との認識の下、さらに大きな木を育てるべく間伐作業に取り組みました。
この頃、「間伐材問題」というのがしばしばマスコミで取り上げられていました。これは「やっと伐採して収入が得られると思ったら、さらに木を大きくするために先送り。間伐はコストがかかる上に細い間伐材の価格が下がってほぼ収入がない。これでは生活できない」という、林業にかかわる人々にとっては切羽詰まった問題でした。解決するには35年生の杉の新たな用途を開発しなければなりません。様々な努力がなされましたが、結局この問題は解決しませんでした。
あれから15年が経ち、多くの木が50年生に近くなってきました。それでもまだ間伐を続けています。15年間でさらに円高が進み、その分外材が値下がりし、つられて国産材も下落を続けました。50年生の杉はもう「成木」です。ここまで成長すると建築材料としても価格が上がり、新たな使途も生まれてくるはずでしたが、結局杉やヒノキが好んで使われる「木造家屋」は激減しました。前回お話しした通り、新たな使途は「集成材」「合板」「パーティクルボード」等ですが、じつはこれらは、おおかたどんな木材からでも生産できます。
「杉は世界で最安値の木材になってしまった」と言われる所以です。

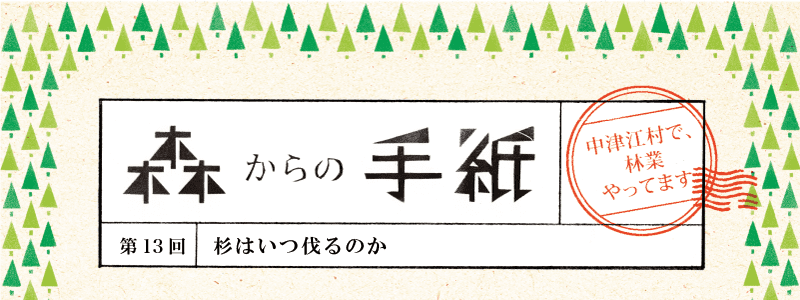

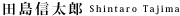
 田島山業株式会社 代表取締役/大分県林業経営者協会理事/(社)九州経済連合会九州次世代林業研究会委員/日田林業500年を考える会会長
1980年慶応義塾大学法学部卒。西武セゾングループ代表室勤務を経て、1988年、父、祖父の急逝に伴い、家業を継ぎ林業経営者となる。日田林業500年目にあたる1991年、子どもたちを対象とした森林環境教育、また学生、社会人の森林ボランティア受入れを開始。「断固森林を守る」取り組みを続けている。
田島山業株式会社 代表取締役/大分県林業経営者協会理事/(社)九州経済連合会九州次世代林業研究会委員/日田林業500年を考える会会長
1980年慶応義塾大学法学部卒。西武セゾングループ代表室勤務を経て、1988年、父、祖父の急逝に伴い、家業を継ぎ林業経営者となる。日田林業500年目にあたる1991年、子どもたちを対象とした森林環境教育、また学生、社会人の森林ボランティア受入れを開始。「断固森林を守る」取り組みを続けている。