 各地の杉はそれぞれの個性に合った用途があったのですが、戦後の復興期から日本中に植林された最大の目的は「建築材」です。丸太は製材所で加工され、板材や柱となる角材となります。しかしこの建築の世界も、日々移り変わっています。吉野の杉は初期成長を抑えるため「枝打ち」を繰り返しますから、建築材としては木目がきれいでフシが少ない「高級材」となります。一時は当地の杉の10倍を超える価格で取引されていると聞き、羨ましく思いました。
各地の杉はそれぞれの個性に合った用途があったのですが、戦後の復興期から日本中に植林された最大の目的は「建築材」です。丸太は製材所で加工され、板材や柱となる角材となります。しかしこの建築の世界も、日々移り変わっています。吉野の杉は初期成長を抑えるため「枝打ち」を繰り返しますから、建築材としては木目がきれいでフシが少ない「高級材」となります。一時は当地の杉の10倍を超える価格で取引されていると聞き、羨ましく思いました。
「住宅展示場」には住宅メーカー各社の最新の戸建て住宅が並んでいますが、驚いたことに住宅内部で「柱」や「板」が見当たりません。白い布が貼られた壁があるだけです。伝統的かつ典型的な日本家屋は、柱や梁を組み合わせて骨格とし、中心の大黒柱が家全体を支えていました。柱をどの方向から見てもフシがないものを「四面無節」などと言って、プレミア価格となります。しかし柱が消え、壁が布で覆われてしまっては、見た目が美しい高級材である必要は皆無です。
もちろん、布で覆われた壁の中には木材がたくさん使われているのですが、目に見えないこうした部分で使うには、むしろ「集成材」「合板」「パーティクルボード」等が使いやすい。集成材は木を小さな角材にカットし、それを接着剤で固めたもの。大根のかつらむきの要領で丸太をスライスし、それを積層して接着したのが合板。チップを接着剤で固めたのがパーティクルボード。技術革新で接着剤の強度は木材のそれを上回り、結果強度を高め、湿気等からのくるいを抑え、使い勝手も良くなるそうです。加工には手間がかかるので無垢の木材と比べるとむしろ高価になるのですが、建設期間が短縮できて後からクレームがつきにくいということです。こうして「高級材」だけでなく「無垢材」の需要もどんどん減っています。
一方、年輪幅が大きい飫肥杉はスライスしやすいそうで、合板の原料として地位を確保しています。吉野の「高級材」に対して一般の杉材を「並材」と呼ぶようですが、要するに枝打ち等の手間をかけた高級材と並材の価格差がグッと縮小したということです。ちなみにすくすくと成長し、どんどん大きくなるように育てた当地の杉を私たちは「健康優良材」と呼んでいます。

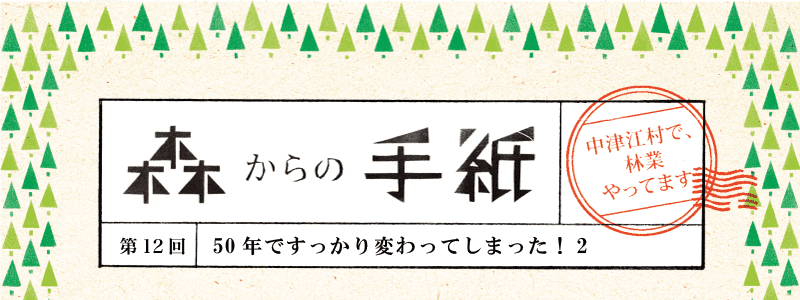

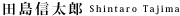
 田島山業株式会社 代表取締役/大分県林業経営者協会理事/(社)九州経済連合会九州次世代林業研究会委員/日田林業500年を考える会会長
1980年慶応義塾大学法学部卒。西武セゾングループ代表室勤務を経て、1988年、父、祖父の急逝に伴い、家業を継ぎ林業経営者となる。日田林業500年目にあたる1991年、子どもたちを対象とした森林環境教育、また学生、社会人の森林ボランティア受入れを開始。「断固森林を守る」取り組みを続けている。
田島山業株式会社 代表取締役/大分県林業経営者協会理事/(社)九州経済連合会九州次世代林業研究会委員/日田林業500年を考える会会長
1980年慶応義塾大学法学部卒。西武セゾングループ代表室勤務を経て、1988年、父、祖父の急逝に伴い、家業を継ぎ林業経営者となる。日田林業500年目にあたる1991年、子どもたちを対象とした森林環境教育、また学生、社会人の森林ボランティア受入れを開始。「断固森林を守る」取り組みを続けている。