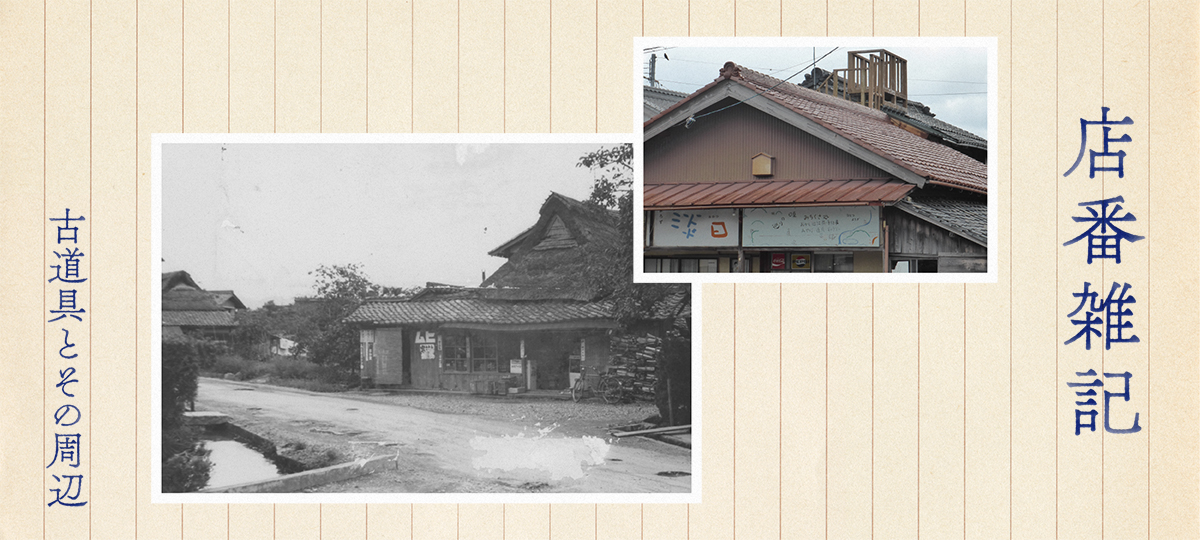北陸本線で滋賀から福井に向かう途中に、新疋田という駅がある。県境の山中にそういうところがあるんだなぁ、と地図上では知っていたが、歴史好きのKさんから「疋田へ行ってみませんか」とお誘いがあった。江戸時代の水路運送の宿場町で、その様子を伝える資料館もあるという。疋田姓として乗り気の古道具担当と3人で訪ねてみることにした。
彦根から疋田までは車で約1時間。途中、古道具担当の提案で長浜市の姫塚古墳に寄る。スマホのナビを頼りに田園地帯を走っていくと、田んぼの真ん中にこんもりした小さな木立がある。それが4世紀前半に作られた前方後方墳で、全長70m。車から降りて古墳の周りを歩いてみると実に長閑な気分に。滋賀は古墳が多い地域で、近所の荒神山の山頂にもあるし、野洲では巨大な銅鐸が多く出土している。
長浜から更に北上し、福井県敦賀市の疋田に到着。山間の静かな集落の入口に、広めの駐車場と小さな資料館と休憩所がある。下調べもあまりせずについて来た店番は、資料館の説明や途中の塩津の道の駅でもらった歴史パンフレットを繰り返し読んで、この地に壮大な”琵琶湖運河計画”があったということを知る。
日本海からの物資を琵琶湖経由で京や大坂に運ぶために、敦賀と塩津を結ぶルートを造る… それは平清盛の発案が最初という。え?そんな昔から…。
清盛案は岩盤の固い深坂峠という難所に阻まれて頓挫したそう。その後の経緯はとてもややこしいので大幅にはしょるが、明治に鉄道が敷かれるまでの間、何度も計画が練られた。江戸時代には高度な測量も行われ、水路、陸路を繋いでの様々なルートが使われた。疋田はその中継地点の一つで、江戸後半に疋田舟川という水路が整備された。しかし川底が浅く船を動かすのに大変な労力が必要なため、廃止されたり、黒船来航の影響でまた復活したり。最終的には江戸末期に廃止、時代が変わり輸送は鉄道メインとなった、とのこと。
資料館の説明パネルには、度々の計画に対して地元の庄屋の反対で白紙に戻るということが繰り返されたとある。ふと、長浜の寺で、集落で保存している仏像を見学した時の話を思い出した。中世の戦から仏像を守るため、度々川底や湖に沈めて隠したのだそうだ。
また、巨大な土木工事計画にも頭がクラクラする。今では巨大な機械で山を掘るけれど、かつては人力。大阪に住んでいた時、近くの生駒山系の麓から大阪城のために寝屋川で石を運んだと聞いた。静かな集落でいにしえの風情に思いをはせつつ、あれこれ余計なことに思いが飛んで、庶民目線の複雑な気持ちになってしまった。
かつて賑わった舟川は、今は整備されてきれいな水路になっている。山から流れてくる水は冷たくて速い。冬は雪深そうだなぁ、などと川を眺めていると、Kさんが「ここには疋田さんはいないらしいですわ」と言う。集落散歩から戻ってきた古道具担当も「疋田さんは住んでないって」と言う。そして「きっと昔はいたであろう疋田姓の人たちは、新勢力に追われ各地に散っていった。古墳のあった辺りは物部といって、物部疋田という氏族が… 」と、長くなりそうな自説が始まった。

「みずうみ」2008年 パネルに麻布、油彩、オイルパステルなど。
戦の繰り返された中世、湖北の集落では、村の仏像を水に沈めて守ったという。