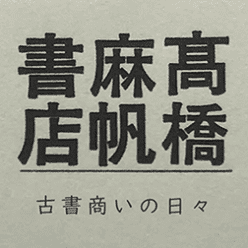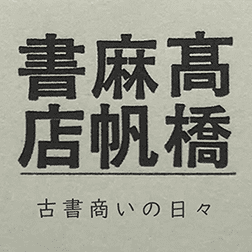今日は何するの?前日ケルンまでの出張で夜遅く帰宅し、今日はどうやら在宅で仕事らしい家主から、朝食時にお尋ね。う〜ん、仕入れ以外には、コンスタンツ通り14番の建物を探すつもり。
あ、ヴィルマーズドルフだね、と返事が。
そこに昔イッテン・シューレという美術学校があって、竹久夢二という日本人画家が1930年頃日本画を教えていたというので訪ねてみたいんだ。イッテンって、ヨハネス・イッテンよ、バウハウスの教師で有名な芸術家よ、とデザイナーの妻が補足。で、グーグルマップで見てみた?と聞かれ、いや〜と、非合理主義でとろい私はもそもそと答えるのであった。見たほうがいいよ、何もないかも。あまり見るべきものが何もない場所だよ。ほらほら、大した建物ではないね・・・
1930年に建てられたものが90年代初めにはまだ残っていた記録ありと金沢の夢二(記念)館の学芸員さんが知らせてきてくれたよ。そうか、そのままの建物だといいね。
こちらではそんなに簡単に壊さないだろうから、ま、そのままであろうと思いながら相槌を打つ私であった。
あっ。友人が何かひらめいたよう。そうそう、その辺に老舗のチョコレート屋があるよ。そこにも行くといい。どこだっけ、そうだそうだ、ここ、ここ。チョコレート屋はブランデンブルク通り17番エーリッヒ・ハーマンという名前。ああ、この包装デザイン知ってる知ってる、昨日、KaDeWe(百貨店)でも見た。
コンスタンツ通りとブランデンブルク通りの交差している角がちょうどコンスタンツ通りの地下鉄駅だ。なんと、イッテン・シューレの住所とチョコレート屋は同じ敷地内ではないか。チョコレート屋はここにいつ店を開いたと書いてある?1928年か。ということは当時のままの建物だろうね。なるほどなるほど。つながりが出てきて面白いね・・・
———-
その後支度して、滞在先のヴォランケ通りからSバーンに乗って出発。ヨーク通り駅まで乗ると地下鉄の7番に乗り換えコンスタンツ通り駅に到着。コンスタンツ通り方面の出口から出ると、果たして二つの通りの交差する角の建物が目に飛び込んできたが、正面一階に入っていたのは靴屋さんだった。建物に近づくと、5本ほどお菓子の包装の筒のような形の説明書き(西欧によくあるポスター用広告塔のような形)が立っているのに気づく。有名なイッテンの肖像写真も目に入ってきた。さすが。バウハウス100周年の記念事業で立てられたらしい。バウハウスとイッテンのかかわり、イッテン・シューレの説明、生徒たち数人のバイオグラフィー、そしてヴィルマーズドルフ地区の歴史に、最後に見つけたのは老舗チョコレート屋の詳しい説明。果たして友人の想像どおりになったのであった。その場所の素っ気なさと対照的に、その説明書きは清潔でとてもドイツらしい良い趣味のものであった。
イッテン・シューレの番地のファサード側は、きらびやかな骨董屋さんになっていた。まさしくバスハウスと真逆の趣味で笑える。古本屋の習性で、古物商と見ると仕入れがあるかとお店に入ってみたかったが、残念ながら閉まっていた。店の脇に中庭に入る通路があり、その奥は歯医者のようであった。入り口に「イッテン・シューレ1929-1934年」と、イッテンの写真と建物の写真の添えられた掲示板があった。
建物をぐるっと回って、ブランデンブルク通りに出ると、チョコレート屋エーリッヒ・ハーマンがあった。西ベルリン時代のまま時間がとまっている。なんだかちょっと錆びついたような風情の淡い黄色の建物だ。やさしい親切なおばさんが店員さんで、お土産をいくつか買い込んだ。それにしても、洒落ているがなんて質素なデザインの包装なんだろう。そういえば、このチョコレート、数年前留学時代の友人が日本に来た時お土産にくれたっけ。再び、コンスタンツ通り側に回ると、ヴァルター・ベンヤミン広場に移転したカント・カフェに向かって歩いた。雨の中、カント・カフェでは薄暗い中で静かな時間が流れていた。