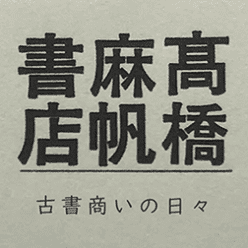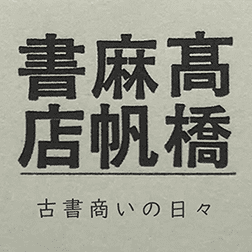ドイツ語の授業後、Sさんが教卓まで来て言った。「先生、髙橋麻帆書店を[インターネットで]見つけましたよ。」「えっ」と固まる私。彼女はさらに続けた。「私、髙橋麻帆書店で本を買おうと思います。」弊店のウェブサイトとオンラインショップを見たのであろうか。
実は、私は古書籍商である以外にドイツ語を教える仕事をしている。こちらは2007年からの仕事なのだから、本屋よりもずっとキャリアが長い。つまりは第二外国語を教えているわけだが、大学での第二外国語をめぐる状況は刻々と変化しつつあり、第二外国語の代わりの講義を受け持っているところもある。近年は、授業の初回の自己紹介の際、「ドイツ語を教える以外に、ドイツ語の古い本を売る仕事やドイツ書を輸入する仕事もしています」と話すこともあるが、店舗を構えない私の仕事の説明は一言では難しいので、あまり話さない。つまりSさんは全くの自力で本屋の私を探し当ててくれたのだ。(※1)
Sさんはさらに言った。「私の欲しい本は、ダンテの『神曲』とアレクサンドル・デュマの『モンテ・クリスト伯』です。」言葉を失う私。とりあえずメモを取り、考えながら帰途につき、メールを打った。「お問い合わせを賜り、誠に有り難うございます。若い方に素敵な本のお問い合わせいただけて感激しております。夏休みに入りましたら一度お目にかかり、もう少しご相談できましたらと存じますが、いかがでしょうか。弊店は、香林坊東急スクエア1階のヴィンテージマーケットに出店しております。冷房も効いていて居心地の良いところなので、良かったらそちらでお話ししませんか? ご都合の良いお日にちをお知らせくだされば参ります。」こうしてSさんは、8月半ば、弊店が2月からポップアップ出店している催事会場に来てくれた。ダンテの『神曲』といえば、ウィリアム・ブレイクのものなどお見せしたかったが在庫がないため、日本で1990年ごろ出版されたギュスターヴ・ドレー挿絵入りのB5の大きさのものと、シュテファン・ゲオルゲのドイツ語訳も、革で装幀されたものが手元にあったので持って行った。後者は書体はもちろん、紙も特別で物として楽しい本だからぜひ触って体験してもらいたいと思った。『モンテ・クリスト伯』の在庫は残念ながら無かった。日本語訳を探す仕事は断るしかないかなと考えながら待ち合わせ場所に居た私に、Sさんは毅然と言った。「先生、私の探している『モンテ・クリスト伯』は洋書です。原文で読みたいんです。」そして、ドレーの『神曲』をすぐに決断して購入。(彼女の即決を見て、ああ、オリジナルがここにあったらと、ドレーの迫力ある版画の線を身近に見せてあげたいとため息が出た…。)さらに彼女は、棚にあった岩波文庫の『イーリアス』をレジに持ってきた。
さて、こうして私の学生さんのための探求書の仕事が始まった。フランス文学を愛する人にとってのテキストの金字塔は、やはりガリマール書店から刊行されるプレイヤード叢書である。どうせなら、『モンテ・クリスト伯』のプレイヤード叢書を見つけてあげたいと願ったが、やはりどう考えても予算オーバー。日本の市場に出ることがあれば、経費がかからないため予算内かもしれないのだが、そんな奇跡が起こるわけはないかと思いながら、やはり簡単にペーパーバックの輸入だろうかと思っていた矢先、用事で上京し、神田の古書業者の競りに参加した。それは毎週火曜日に行われる洋書会という古い歴史を持った神田の古書の市場である。とても久しぶりの参加だったので、改めてかつての勤め先の師匠が皆さんに紹介してくれた。神田で働いていた頃、毎週通った日々がつくづく懐かしい。先輩方は「久しぶり」とあたたかい声をかけてくださりありがたかった。
さて出品物を見てみると、プレイヤード叢書が二口あった…。引き寄せられるように近づくと、数ある一冊の背にLe Comte de Monte-Cristoとある。奇跡が起こった。無事に落札できて、その本は今Sさんの手元にある。

ところで、プレイヤード叢書といえば、私の心にはいつもかつて働いた至成堂書店の棚が浮かんでくる。至成堂書店については、また次回記したいと思う。日本にも、昔は洋書屋さんの存在がありふれていたと思うが、街にはもうずいぶん洋書の棚が少なくなってしまったと感じている。唯一手の届く存在だったレクラム文庫やインゼル文庫の背の棚を丸善でじっと眺めたことなど、懐かしくてたまらない。若い人に、私がかつて見た洋書の棚を見せたいなと考えながら、Sさんが元気に訪ねてくれた本棚の本を増やした。
※1 講義を持っている大学では、「書物」をテーマに講義させていただいており、私の仕事について話す機会をいただいてもいる。ただ非常勤授業のほとんどはドイツ語の授業であるので、本業について話す機会はほとんどない。
2024年10月17日