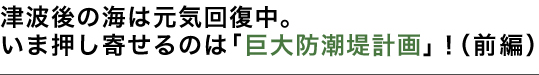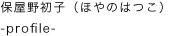みなさん、はじめまして。最近、『チルチンびと広場』に仲間入りさせてもらった日本自然保護協会(Nacs-J―ナックスジェイと呼んでください)です。忙しいスタッフに代わって新米理事である私が、Nacs-Jの活動フィールドでの熱いトピックスをお伝えし、みなさんといっしょに考え行動していけたらと願っています。「自然保護」の始まりや考え方について前置きしたいところですが、余裕があるときのためにとっておくことにして、いきなりですが話題に入りましょう。
まっさきに、いますぐ、みんなで考えなくてはいけないことが、復興中の東北地方で起きています。
大津波で被災した海岸に「巨大防潮堤計画」が押し寄せているのです。それって自然保護問題? と思う人がいるかもしれません。でも、震災後、人間は“生きている自然”とどうつきあっていけばいいのだろう……と深く考え込んだ人は多かったのではないでしょうか。正解はなくとも、そのヒントは、喜怒哀楽の激しい自然とそこで長いあいだ付き合ってきた海の民や山の民、里の民が教えてくれるにちがいありません。日本列島のどこにでもいた私たちのご先祖たち、その後継者たちが。その声を聞き取り、学ぶことも自然保護につながるのです。
そこで、防潮堤の前にカキの話を。個人的なことで恐縮ですが、私はカキが大好きです。美味しい日本のカキのなかでも、ぷっくり肥えてなにか澄んだ香りのする三陸のカキは毎冬の楽しみ。ですが、津波で養殖業が壊滅したため、このふた冬は食べることができませんでした。あのカキを産んでくれた「森は海の恋人」の海は、いったいどうなっているのでしょう?
森は海の恋人ってご存知ですか? そう、魚貝類や海藻などの海の幸は、森がつくりだした養分を川が仲立ちとなって海に届けることで、プランクトンを通して魚や貝を肥え太らせている、という森と海のつながりの大切さのことです。赤潮でカキが赤くなった1960年代にそう気づいた三陸の漁師さんたちが、上流の山村に広葉樹を植えようと呼びかけて実践したキャッチ・フレーズ。全国に広まり、山―里―川-海が近い日本ならではの流域保全運動として、今や子どもたちが参加する人気の環境教育にもなりました。

「森は海の恋人」の環境教育活動 - 写真提供:NPO法人森は海の恋人
陸からの淡水と海水が混じる河口や沿岸は「汽水域(きすいいき)」と呼ばれ生き物がたくさん生まれ集まるところで、古くから人は「なりわい」のために大切に使ってきました。そこを「森と海が恋をする場所」と、ロマンチックな言葉でよみがえらせたわけです。大津波はしかし、人の営みもろともその逢瀬を破壊してしまいました。
<後編につづく・7月下旬掲載予定>