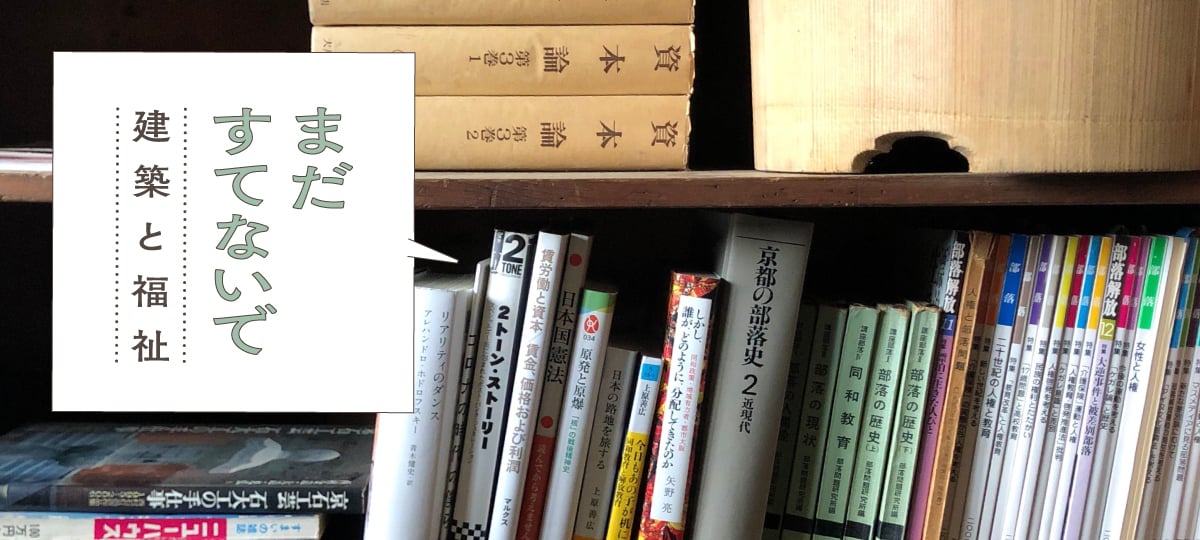京都駅近く、崇仁〜東九条あたりに通っている。
崇仁は、元被差別部落である。その南隣にある東九条、通称トンクと呼ばれる地域は、コリアンタウン。
かつて、この一帯は、西日本最大級のスラムだった。
この地域の歴史、かつての暮らしについて、今まさに、聞き取りを始めているからなのか、サッと簡単に説明してしまうことに抵抗がある。僕自身、まだ何もわかっていない気がするから。
苦肉の策として、Wikipediaのリンクを貼っておく。これは、あくまで基本情報。
書き手として誠実ではないことは承知の上。どうかかんべんして欲しい。
崇仁(京都市)*東九条についても記載あり
さらに詳しい情報が知りたい場合は、「崇仁 論文」「東九条 論文」等で検索してみるのもおすすめ。
ご存知の通り、崇仁には、京都市立芸術大学が移転し、東九条には、2025年秋にチームラボ・バイオヴォルテックス京都がオープン、現代アート作家、村上隆氏の大型アトリエ建設も予定されている。
2019年に開館したTHEATRE E9 KYOTOも含め、新しい文化芸術の街へと変わろうとしている。
駅近の再開発地帯として地価も上昇。性急な不動産開発によって、住民が街へ参加する機会を失ってしまうのはいつものこと。
ジェントリフィケーションの一例として、一言もの申したいところではあるが、この地域の特殊性を考えると慎重にならざるを得ない。
部落差別は、「地域」に対する差別でもある。東九条のように被差別部落の周辺に朝鮮人居住区ができることも多い。
不良住宅地区とも呼ばれたこのエリア、物理的レガシーを残す意味を見つけるのは難しい。
更地にし、風景そのものをごっそり変え、負の歴史を封じ込める。
それもやむなし。といったところか。
少し前にベトナム、ハノイについて書いた。
ハノイを好きな理由は、街並みから「かつて日本にもあった風景」を見出し、昭和的ノスタルジーを感じているからだと思う。
個人的に元気をもらえる映画のひとつが、旧赤線地帯を舞台にしたポルノ映画『(秘)色情めす市場』(1974年 監督:田中登)。
ストーリーもさることながら映画に映る70年代、大阪・釜ヶ崎の街並みにグッと来る。
両者とも、街が活気に満ち、適度に汚く、カオスがある。
「昔の方が良かった」という感覚は、危なっかしい。物見遊山程度では、そこに住む人の気持ちはわからない。特に崇仁、東九条のような場所では、うかつに口に出せるような言葉ではない。
一方、単純に「風景として好き」という気持ちもある。
この壮大なジレンマを少しでも解消するため、土地の歴史を頭に入れておき、ぼやっとでもいいので意識しながら街を歩くことにしている。
ハノイなら「植民地」や「戦争」、崇仁、東九条は、いわずもがなの「差別」の歴史。
その意識があると、何気ない街のディテールも楽しめるし、変わってしまった風景にも「これはこれで意味がある」と思うことができる。
普通におすすめの街歩きテクニックだ。
風景は変わっても、差別の歴史が消えるわけではない。むしろ、精神的なレガシーとして残す意味はある。と、思うのだがどうだろう?
被差別部落、在日朝鮮人問題は、最も身近にあるハードな人権問題であり、ケーススタディとしてこれほどわかりやすいものはない。
ただ、「差別」というものには、感情と様々なイデオロギーがないまぜになった複雑な事情がある。情報を収めた、資料館的なものだけで語るには限界があるかもしれない。
肌感覚として「差別、ゆるすまじ」となっていくためには、やはり芸術が一番いい。「災い転じて福となす」ことができるのも芸術だけだろう。
チームラボや村上隆さん、その辺のこともふまえ、この地域らしい作品を作ってもらえないでしょうか?