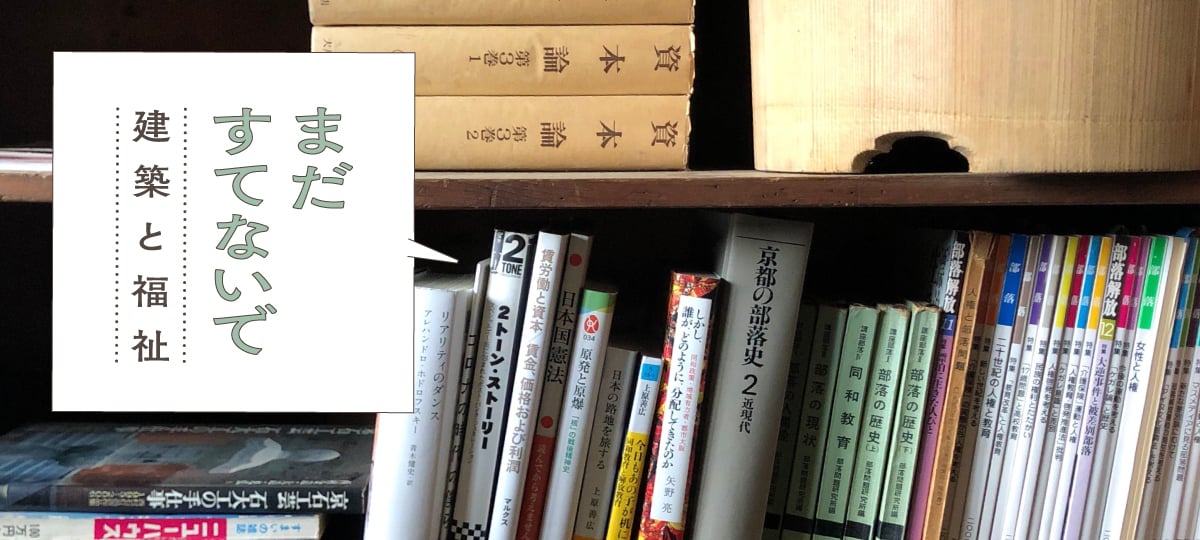0えんマーケット(以下0えん)の常設から1年が経った。
週2〜3日、安定してオープン出来ている。
*0えんマーケットについて、以前の記事はこちら
まずは、物品、活動資金を寄付していただいた方、ありがとうございます。
おかげさまで、大きな問題もなく、ごきげんに運営できていることを報告しておきます。
その要因として、現場に立つボランティアメンバーが、40〜60代の女性で固定されてきたことが挙げられるかもしれない。
ホスピタリティ精神をいやみなく発揮できるのは、この世代の女性が持つ強みなのだろう。
わかりやすく言うと、場の社会的意義をアピールする前に「おなかすいてない?」の一言が出るような、飾り気のない応対ができること。
あらゆる人を受け入れている場所では、ものすごく大切なことだ。
0えんを常設している我々の拠点、「麓」の内装工事は、相変わらず進んでいないし、組織としてのレギュレーションもゆるい。合言葉は「個別対応(その場しのぎ)でお願いします」。
都合よく考えすぎだと思うが、ほどよく力の抜けた運営が功を奏しているのかもしれない。
そして、一番気がかりだった、在庫管理について。
古物商を生業とする僕にとって、在庫過剰は、最も警戒する要素でもある。
買取など、受け身の仕入れをせざるを得ない古物商は、たくさん引き取って、その中にあるわずかな「売れる商品」もしくは、「売れそうな商品」で勝負しないといけない。
実際は、何年経っても売れない商品の方が多く、それらが置き場所と経営を圧迫する。
金銭を介さない状態での不用品受け入れは、ゴミの処分もタダではない昨今、割と危ない。商品が雑多になればなるほど、需要の予測も立てにくく、物品のコントロールは至難の業となる。
在庫過剰になることは、ある程度予想していた。
ところが、在庫は増えているのだが、過剰というほどでもない。ちょうどいい感じに保てている。冬物、夏物など、季節に合わせた衣類のストックもできるようになった。
在庫過剰やむなしと思われた事態は、見事に回避されている。
なぜこのような状況になったのかは、まだわからない。ただ、少しずつわかってきたこともある。どうやら、物品を持ち込んでくる人たちが、何が必要なのか? 予想以上に気を遣ってくれているようなのだ。
寄付をしてくれる人の多くは、0えんの利用者でもある。交換するように、何かを持ち帰る。これはもう、お客さん自身が在庫管理をしている状況なのでは?
余計な決まりごとを作らず、場さえあれば、モノは自然に流れていくのだろうか?
僕らのような地域活動は、参加意識を高めるため、サービスを提供する側、受ける側、両者の境界を曖昧にすることが大切だと考えている。
組織やリーダーは必要なく、かつての「井戸端」のように、ただ場があり、最低限の管理で運営できれば、それがベスト。
1年がたち、少し理想に近づいたような気がしている。
素直にうれしい。