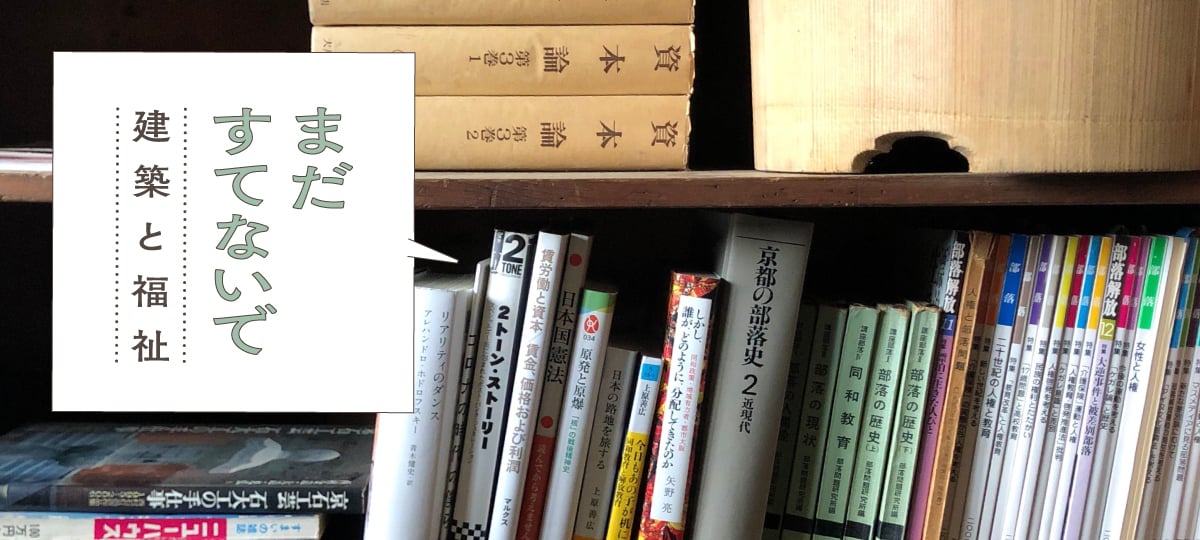9月にベトナムの首都、ハノイに5日間滞在した。
観光らしい観光もせず、ずっと散歩をしているような日々が今の自分にあっていたのかもしれない。ハノイロス。と言ってもいいくらい、感傷的な気分が続いている。
ハノイの街はさわがしい。
たくさんの車、バイクが半ば交通ルールを無視しながら行き交い、歩行者の多くは、場馴れしていない観光客。
高級店の店員でもヒマになるとすぐスマホ、書店では積み上げた本をテーブルがわりに昼ごはんを食べている(本当の話)。
あらゆるタイプの「衝突」が起こりそうなところをギリギリ回避しているような印象。それでも舌打ちから、取っ組み合いのケンカになってもおかしくない。だが、そんな場面は、一度も見かけなかった。
とんでもないカオスなのに治安はいい。というのは驚異的だと思う。
ハノイには、世界でも珍しい「女性博物館」がある。
母系社会の少数民族、独立戦争における女性兵士の功績など、大量の資料が展示されている。
現在、ベトナムでは女性の労働力率が70%近くあり(日本は女性48.2%、男性70.8%)世界水準よりもかなり高いそうだ。
ベトナムにもジェンダーギャップはあるだろう。ただ、オフィス街でも下町(旧市街)でも、確かに働く女性の存在感は際立っていた。
ベトナム料理教室にも行ってみた。
これは、慎重に言葉を選ばないといけないが、庶民的なベトナム料理に高度な技術は必要ない。と思う。美味しさの差は、「丁寧にダシを取る」とか、それくらいだろう。小手先のアレンジを必要としない、シンプルで堂々とした日常食。食料自給率160%の余裕だろうか?
街中には、そんなベトナム料理店がとにかく多い。フォーやバインミーなど、ジャンルの違いはあるにせよ、僕らのような外国人から見たらメニューも店構えも大きな差は感じない。
しかも、これほどローカル店ひしめく状態なのに、料理や内装で競争をしているようには見えない。客の取り合いが激しい日本の事情から考えると、ずいぶんのんびりしているように思える。
行動経済学の研究では、市場のなかで女性は「リスク回避的」であり、男性より競争を避ける傾向があるとされている。
これは、仮説にも満たない、僕の感想なのだが、あのカオス状態での治安の良さ、あるいは、無駄に競争をしない店のあり方は、ベトナムの社会が「女性的」であるからのような気がする。
フェミニズム。という言葉に対し感情的に反応する人は、それを「絵に描いたモチ」のように捉えてしまうからだ。
主義うんぬん以前に、いたるところでモチを焼いているのがハノイの街。
例えば、街中のゴミ回収作業は女性が担っている。もちろん正当な労働者として。それだけでも、彼女たちがいないと街が成立しない実感がある。
実は、僕自身も、自分の中にあるフェミニズムが何であるのか? 判然としない部分があったのだが、今回の滞在で少しクリアになった。
それは、平和であるということかもしれない。さらに言うなら、街場で生きる生活者の平和。
カオスを隠そうとする日本の街は、清潔で機能的。公共での倫理性も高く、マナーも守る方だろう。しかし、街に出れば、誰でも心の中で舌打ちするようなことが1回や2回は起きるはず。
実際は、ストレスが地層のように積み重なっている。これが何も起こさないという保証はない。
もしも平和を願うなら、制度や態度で女性の邪魔をしない方がいいかもしれない。
後編につづく。