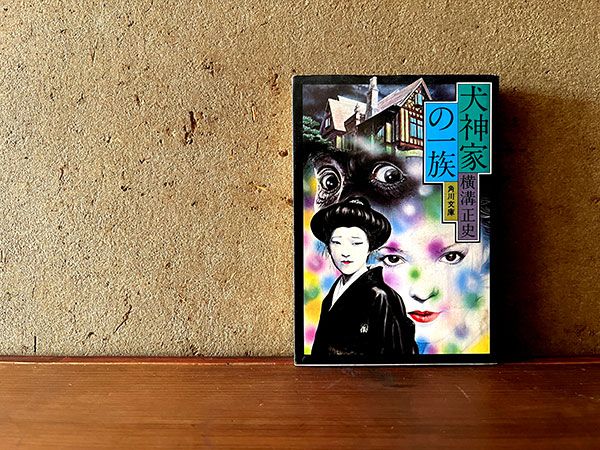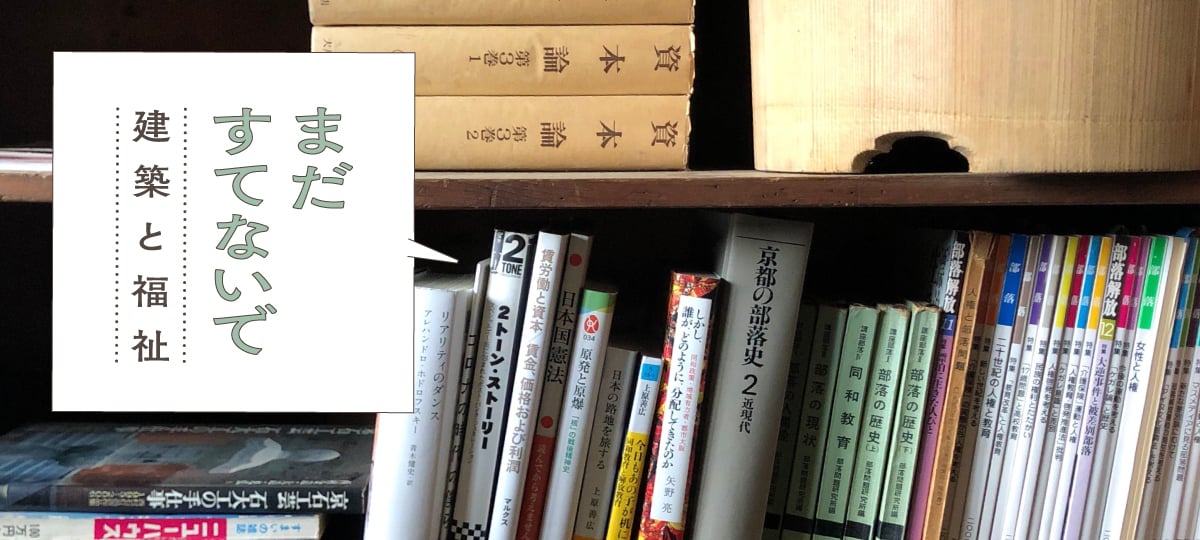いわゆる「家じまい」の手伝いをしている。
今、生きている人たちがいなくなれば、この「家」を継ぐ人はいない。つまり、家系を閉じることでもある。
このご時世、特に珍しいことでもなく、僕自身も同じような状況を抱えている。おそらく、僕の代で松本の家系は途絶えてしまうだろう。
空き家問題や福祉に関わっていると、「家」が抱える難題に直面することも多い。
家財整理など、物理的に「家」をしまうことについては、それなりのノウハウがある。しかし、精神的な意味での「家」、つまり家族間の問題は、感情が支配する割合が多く、一筋縄ではいかないことも多い。
お茶碗ひとつ処分するにも家族の思いが交錯する。当然といえば当然なのだが、作業は滞る。
そんな経験もあり、自分の「家」については、意識的に感情的な話を避けるようにしている。
やるべきことははっきりしている。家系が途絶えたとて僕自身の生活は変わらない。必要以上に大ごとにせず「はい、よかったよかった」と軽く締めて終わるのがいい。
ところで、「家」がテーマの映画といえば、横溝正史原作、市川崑監督『犬神家の一族』(1976年)を思い出す。
大富豪の当主死去による相続のごたごた、挙句の殺人事件。そして名探偵登場、犯人を突き止める。
ありがちなストーリーではある。
ただ、この映画のみどころは、謎解きミステリー要素ではない。うずまく感情によって「家」自体が巨大な怨念と化すような、状況そのものにある。
映画の素材としては、幽霊やゾンビなど、超自然的現象の方が、より恐怖を感じる人もいるだろう。
しかし、犬神家の恐ろしさというのは、家父長制、土着的因習、そして戦争がもたらす理不尽、あくまでも人の所作にすぎない。そこに金と欲がからみ、人は、狂気に取り憑かれる。
その業の深さたるや。陰影を強調した不穏で美しい映像も相まって、みるたびに戦慄している。
先日、選択的夫婦別姓制が実現すれば「家族の絆がうすれ、日本人としてのアイデンティティも失われる」的ニュアンスの発言を聞いた。
あたかも保守的(伝統的)な家族観が理想であるかのような言いっぷりだが、犬神家のように災厄をもたらすことも少なくはない。いや、むしろ多い。
血縁としての「家」が不幸を招く。という設定は、源氏物語や枕草子など、古典にも数多く見られる。1000年以上前から、血縁は「やっかいなもの」として物語に登場してきた。
良くも悪くも、制度が変わったくらいで「家」の呪縛が解けることはなく、家族にまつわる愛憎劇も終わらない。
100年後も「家父長制ってやっぱりダメだな」とか言いながら『犬神家の一族』をみているのかもしれない。