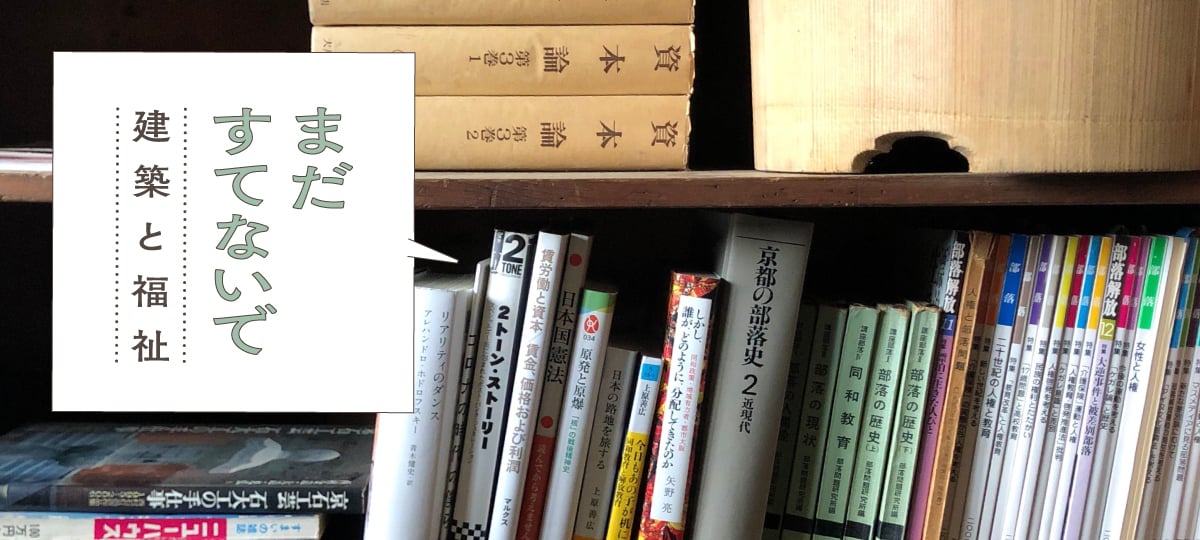ハノイの観光地、旧市街に並ぶ建物は、間口が狭く奥行きのある、いわゆる「ウナギの寝床」。ベトナムでは、ウナギどころの長さではなく、ものによっては100mもあったりするのでチューブハウスと呼ばれるそうだ。
1階が店舗、上階が住居空間、という区分けが多く、ベトナム、中国、ヨーロッパと、様々な意匠があり、折衷もしている。
そこに看板や、歩道にはみ出した客席、売り場が加わり、旧市街全体が、モザイクやコラージュのような、カオス的情景を作っている。
街が「ちゃんと汚い」こともポイントだ。
旧市街を散策中、飲食店の店先に「あってはならないもの」を見かけたのだが、数時間後もまだそのままだった。ローカルの人にとっては、「あっても気にならないもの」らしい。
ベトナムの生活や人間性が丸出しである一方、大観光地でもある。これは、かなり特異なことなのかもしれない。
特異なことはまだある。
旧市街には、観光地としての建築規制もあるそうだ。しかし、その規制が施行されたのは2013年。「旧市街」と名乗る割には、えらく最近に思える。
もちろん、その時点でも観光地だったので、規制ありきの街並みではない。今でも違反に対する罰則が軽いためか、守る人も少ないそうだ。
カオスをカオスのまま放置することで成り立つ観光地。
そこには、前回書いたようなベトナム人の精神性も深く関わっているのだろう。
一方、僕が住む京都。
先日、旧市街っぽいニュアンスをかもしだすゾーン、錦小路を久々に歩いてみた。
噂には聞いていたのだが、かつての「京の台所」的イメージは、消滅しつつある。海鮮や和牛といった、京都にはあまり関係なさそうな店も多く、びっくりするくらい観光客向けフードコートと化していた。
人の往来も以前より多い、一瞬、通りに入ることをためらったが、いざ歩いてみると、これが結構楽しい。
方向性は異なるが、ハノイ旧市街で感じた、カオスがもたらすパワフルさと似ている。もっとわかりやすく表現すると、なにがなんだかわからないが、とにかく盛り上がっている。この熱気は、観光地として必要なのかもしれない。
ただ、この雰囲気は、日本全国どこでも見受けられる。
祭り感を演出するための屋台風であったり、カフェではない、カフェ的内装の店があったり。食べ物は、とりあえず串に刺す。地元の食材をソフトクリームにねりこんだりするのもありがちだ。
熱気を演出する装置としては有効だが、どこか白々しい。
錦市場には、昔ながらの風情をキープしている店もわずかに残っている。
インバウンド仕様のなかでは、そんな店の方が印象に残るし、むしろ目立っている。皮肉な現象だ。
ハノイ旧市街のカオスは、もっと、ゆるやかに進行したのだろう。時間をかけて、土地や人に馴染んでいったため、あるべき自然な姿になっている。
あわてずさわがず現状維持。
というのが、最終的に生き残るのかもしれない。